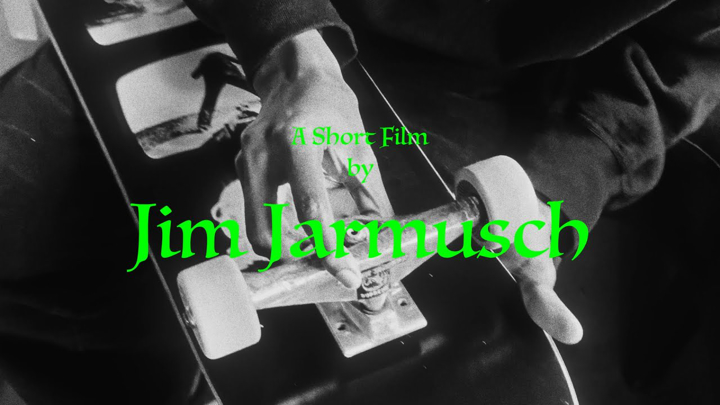「ゼッタイニバレマセン。ホンモノトイッショデス…」。高2の春、放課後に上野のアメ横をフラついていた。怪しい露店があり、これまた怪しい外国人店主にそう言われた。その露店には、高級腕時計が所狭しとならんでいた。いや、高級腕時計に見える腕時計である。ニセモノ…。僕はその中のロレックス(エクスプローラー)を手にし、静かに眺めていた。ずっしりとした重みにしっかりと輝きもある。「ジドウマキデス。ホントウニヨクデキテイマス…」。僕は悩みに悩んだ。「意外とありかも…」。僕はそう自分に言い聞かせ、貰ったばかりの少ないバイト代から2万円を外国人に渡し、さっそく腕にはめてみた。外国人は僕に言った。「スゴクステキデス」。
僕が通っていた高校は、上野の隣にある鶯谷が最寄り駅。鶯谷は都内有数のラブホテル街である。上野の繁華街、そして吉原という色街が近いため、立地的に鶯谷にラブホテルが栄えた、らしい。僕は毎朝、駅のホームで立派なスーツを着た大人の男性と女性のペアが、おそらくそのまま会社出勤するであろう姿を横目でガン見しながら登校していた。Yシャツの後ろの襟に、ガッツリ真っ赤な口紅のキスマークがついてるサラリーマンを見かけたときは、大人の世界はどうなってるんだ…? と強く思い、また悶々としながらラブホテル街をぶった切り登校していた。

そんな影響もあってか、当時の僕は大人の男に憧れていた。いかに周りの女子たちにイケてると思われるには? と試行錯誤を繰り返していた。一方で、流行りには絶対に乗らないと決めていた。周りの同級生の男子は、揃って茶髪にし、当時流行っていたツイストパーマをかけていた。僕はあえて短髪で黒髪。それをギャッツビーのジェルでツンツンにしていた。女子の中でもまだルーズソックスが流行っていた時代だったが、その中でも紺のハイソックスを履いている少数派の女子には、おまえらわかってんじゃん! と、上から目線で見ていた。
そんな勘違い野郎の僕に、神からの啓示が下りた。「そんなあなたには、腕時計がよいざますよ」。オッケー!! ラスタファーライ。僕はさっそく書店に赴き腕時計専門誌をゲットした。ロレックス、オメガ、タグホイヤー、その三社の腕時計に心を奪われた。「できる男は腕時計で決まる」みたいなキャッチコピーに、(うんうん。まさにそのとおり…)と、いとも簡単に洗脳されたのだ。ただ、僕のお弁当屋さんでのバイト代では到底手に入るような代物ではない。3万の貯金でも、2年以上かかる。やはり、諦めるしかないのか…。そんな時に出会ったのが、アメ横でのロレックスである。
「マジ!? ロレックスじゃん」。「大本くん、まじカッコいいんだけど」。
僕の想像を超える周りの反響に、「えっ!? まあ、ちょっとね。あんま見ないでよ」と平静を装った。が、高校生の分際でゲットできるものではないのは、みんなわかってる。「でも、どうしたのそれ?」とさっそく問いただされる。それも想定内。「いやー、オレのおじいちゃんが腕時計マニアでさー。で、この前の誕生日にくれたんだよねー」。僕は昨晩真剣に考えた末に作り上げたストーリーをみんなに力説し、無事にロレックスライフをスタートさせた。

その年の夏、僕は横浜みなとみらいの花火大会に行った。笑顔が可愛いく優しい、僕なんかにはもったいないくらいの彼女との初の遠出デートである。「花火超楽しみ〜、テンションあがるね、ヨッち!!」。そんな彼女に「花火くらいで、そんなにはしゃぐなよ」と、一応クールぶっとくも、心の中では「うひょー! 女の子と花火に行くという、中学からの夢がもうすぐ叶うぜ!! 帰りは鶯谷のラブホ誘っちゃうぞ! やっべえ、バイト代速攻なくなるぜ!! ポッポ〜!」っと、僕はおそらく彼女以上にテンションMAXで、荒くなる鼻息を必死に堪えていた。
花火開始までまだ時間があったので、僕らはビルの地下街にあるお好み焼き屋で食事をとることに。「オレさー、小2まで瀬戸内海の小さな島で育って広島近かったから、うちで作るお好み焼きはいつも広島風だったんだよねー。つーか、それがお好み焼きだと思ってたけど、東京引越して初めて関東風のお好み焼き見たときびっくりしたよ。やっぱ、お好み焼きつったら広島風でしょ。まあ、関東風の方が食べやすいけどね」っというような、どうでもいい糞トークの数々を、彼女は「うんうん、それでそれで」っと笑顔で聞いてくれていた。そんな彼女との時間が、僕の胸をさらに踊らせた。

ガッツリお好み焼きを食べ、落ち着いたころ、僕はなにやら視線を感じた。僕たちはテーブル席に座っていたのだが、カウンター席に座っていた軽くBボーイ風の明らかにヤンキーふたり組がこちらをチラチラ見ている。年は二十歳前くらいだろうか? なんだあいつら。オレらが幸せそうにしてるから嫉妬してるのか? 花火大会に野郎ふたりでダセーな…っと心で思いつつも、僕の心拍数は急激に上がり始めていた。嫌な予感が…。そして、ヤンキーのひとりの言葉がはっきりと僕の耳に入った。「あのガキ、生意気にロレックスしてんじゃん」。ふたりは不敵な笑みを浮かべながら、コソコソと何か話している。「やばい…ロレックス狩りにあう…」。僕は緊張のボルテージがMAXになり、全身が震えだした。「ヨっち、どうしたの急に?」。彼女も僕の異変に気付き、不安な表情を浮かべている。「いや、別に…」。ふたり組は会計を済ませ店を出たが、店の前で待機している。そして、わざわざ顔を覗かせながら僕を何度も見てくる。違うんです、これはおじいちゃんから貰ったロレックスではなく、怪しい外国人から2万円で買ったロレックスなんです…どうか許してください…。そう祈った。心からニセモノだとバレたいおかしな事態となっている。彼女が、「そろそろ行こう」っと言ったが、いや、まだ出れない。外にいるヤンキーふたりが、オレのロレックスを狙ってるヤツらが行くまで出れない…。彼女から笑顔が消えた。僕らは沈黙のなか、粘りに粘り、店内に居座り続けた。外からは、腹に響く花火の音がなり始めたころ、ふたり組はどこかへ消えて行った。「よし、行くぞ」。僕は彼女の手をとり、猛ダッシュでビル地下街の一番端っこの出口まで走り外に出た。外にはたくさんの人が溢れかえり、歓声を上げていた。僕らもちょうどよいスペースに腰掛け、花火を見た。ただ、僕はずっと身体の震えが止まらず、花火どころではなかった。まだあいつらこの辺にいるんじゃないか? あんなに楽しみにしていた彼女も、言葉がない。こんなクソダサい僕に呆れていたのかもしれない。花火が終わり、いつもとは違うぎこちない笑顔で彼女が言った。「すごくキレイだった…連れてきてくれてありがとう…」。僕は泣きそうになった。本当にすまん…。その夜は、彼女を鶯谷に誘うどころでは到底なかった。

その日以来、僕はロレックスを上野や池袋や渋谷などの繁華街に出るときは、身に付けないようにした。ただ、学校では相変わらず、ロレックスライフを楽しんでいた。そんなある日、僕はクラスの仲間と廊下で弁当を楽しく食べていると、他のクラスのたまに挨拶するぐらいの男子が声をかけてきた。「大本くん、それロレックスじゃん、すごいね。僕もロレックスいつか欲しくてさー。ちょっと見せてよ」。僕はいつもの調子で、彼にロレックスを手渡した。彼は、みんなと違い、入念に僕のロレックスを見てこう言った。「大本くん、もしかしてこれ上野で買った?」。
Σ(゚д゚lll)⁈
全身の筋肉が硬直した。「う、う、上野!? さー、これおじいちゃんから貰ったから、どこで買ったかは…」。彼は一瞬ニヤリとし「あ、そうなんだ」っと吐き捨てるように言うとその場を足早にたち去った。周りの仲間が「なんで、上野で買ったと思ったのかな?」っと不思議そうにしている。僕は慌てて、「知らね…つーか次の5限、生物じゃね? だりー。オレ、保健室で寝てくるわ」っとその場をやり過ごす。
僕は保健室のベッドで天井を見上げながら、無性に悲しく、そして今までに感じたことのない虚しさが襲ってきた。ニセモノはわかるヤツにはわかる…。そしていつか必ず暴かれる。なにより、自分がニセモノだった。ニセモノのロレックスが似合う人間だったのだ…。
僕はロレックスを腕から外し、5限目の終わりを告げるチャイムが鳴るまで浅い眠りについた。

DESHI
旅とドトールと読書をこよなく愛する吟遊詩人。 “我以外はすべて師匠なり”が座右の銘。