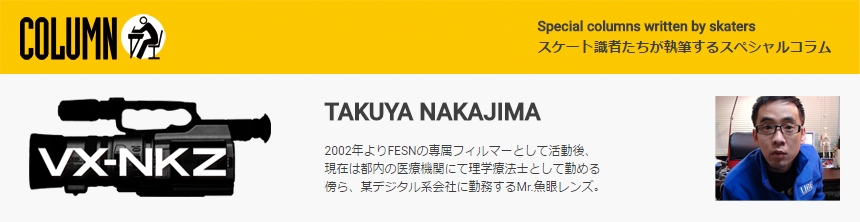当時の移動手段はすべて電車・バスなどの交通機関で、どこでも撮影させてくれるスケーターがいれば足を運んだ。大会やパークで連絡先を交換して電話連絡。「デートしたいと思う女の子がいたらメールより電話だろ!? だから撮影したいヤツがいたらとりあえず電話しろ」と先輩に教えられたことを僕は実直に実践していた。
どこか撮影できそうなスポットやトリックについて打ち合わせてからひとりアウェーな環境に飛び込んで行く。そうすると、もちろん相手のペースになるのは当然の流れ。当時撮影するスケーターはほとんどが年上で、当たり前だけど僕よりスケートが上手い。スケートスキルで立場が微妙に変わってくることは、スケーターならば分かって頂けるだろう。
特に愚痴をこぼすわけではないが、撮影が思い通りにいかないのはよくある話。いいスポットがあるからと東京の僻地まで行っても…。なんてことは日常茶飯事。コストパフォーマンスを考えようなんて北極と南極ぐらい遠い話。それでも知らない町に行って、ローカルスケーターたちとビデオカメラを通して一戦交えることは楽しいことだった……とポジティブに捉えるしかない。あまり大きな声では言えないが、よく車の洗車にも付き合わされた。なんで人の車なんて洗ってるんだ……と思いながらも、洗車をしながらコミュニケーションを計って信頼関係の構築。とポジティブに捉えるしかない。遠回りでも撮影したいと思ったからこそ付き合えたことだった。突然、見知らぬスケーターとフィルマーが撮影しに行って「撮れたからさよなら」というのも味気ない。洗車がしたいとまでは言わないが、ある程度の人と人との繋がりは大事にしたいと思っていた。大事なことは目に見えにくいのかもしれない。
そんなコミュニケーションの中で印象に残っているのは、国分寺のスナック(?)で始発まで過ごしたこと。国分寺まで赴いて撮影したかったスケーターは、もちろんKign of 西東京の145こと荒畑潤一くん。今となっては、どこで初めて会って撮影するようになったかハッキリとした記憶はないが、初めて撮影したときから意識の高いスケーターだと思ったことは鮮明に記憶している。別の言い方をすれば、145くんのところに行くと必ずフッテージが残せる。そんなスケーターのひとりだった。それでも何度か撮影を続けると、うまくいかない日があるのは当然のことだろう。
僕は正直、その日はもう撮れなくても仕方がない、と思い始めていた(撮れない日は撮れないし、撮れる日は撮れる)。それでも145くんはフィルマーをわざわざ呼んだという申し訳無さと、なにか仕事をしなくてはという責任感にかられていたようだ。朝からスケート三昧で疲れているはずなのに、夜の遅い時間なら撮影できそうなスポットがあるからと、終電ギリギリまで粘って撮影していた。結果的には何も撮れなかったし、もちろん終電も逃した。
さすがに国分寺から中野まで車で送ってもらうのも忍びないので、駅前の漫画喫茶で朝まで過ごそうかと考えていた。朝まで異国の地(?)でゆっくり過ごすのも悪くないし、なによりも疲労困憊の身体を休ませたかった。けれども145くんは「終電を逃したなら朝まで付き合うよ」ということで、スナックに連れて行ってくれたのだ。僕よりも数倍疲れているであろう145くんが、朝まで付き合ってくれたことの優しさに触れられたこともうれしかったし、なによりもあの不思議な空間で、夜通しスケート談義をしたことが今でも大切な思い出のひとつとして胸に刻まれています。