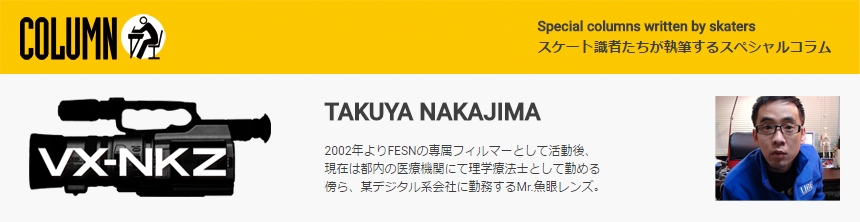真っ青な空と青い海、まったく風のないビーチに、エレガントな女性がこんがり焼けた肌を露出しながら歩くロサンゼルスのビーチ。僕はこのシチュエーションで憧れのスケーターを撮影して、そして大きな失態を犯してしまったのです。今となってはいい思いでですが、当時は結構ヘコみました。
その時ぼくは『overground broadcasting』の撮影でクイム・カルドナの家(冬季の間だけ西海岸に移住していました)に滞在し、パウロ・ディアスやビリー・バルデスを撮影していました。約10日ぐらいの日程で僕に課せられた使命は「世界に挑戦できるフッテージをできるだけ多く残す」こと、ただそれだけです。当時の僕は怖いもの知らずというか、無鉄砲というか、誰よりも多く撮影するという気持ちだけをもって海を渡りました。けれど知っているのはクイムと超不思議人間のパウロ。しかもLAの移動手段は基本的に車でなすがまま…。
それでも初日には、クイムがヤバいスケータがいると言って連れてきたのがグレック・ルツカ。今では有名ですが、当時はあまり名の知られていないスケート少年でした。僕は彼の名前にまったくピンときませんでしたが、一緒にスポットに行くとクオリティの高いスケートに絶句しました。ハンドレールオーバーのFs 360を見た時に思ったことは、そこらの無名な少年がこんなトリックをメイクするなんて「アメリカハンパない」って本当に思いました(後から彼をメディアで見るようになり、少しほっとしました)。
冒頭の映画のようなワンシーンはロサンゼルスのサンタモニカビーチのサンドギャップです。昼過ぎにクイム、パウロ、ハリー(NYの絵を描いてる人)でスポットに到着し無事にクイムとパウロのフッテージを取り終えたところ、燦々と降り注ぐ太陽の下にあの人が現れたのです。真っ黒でタイトなパンツに真っ白なピタT、髪はモヒカン頭のしゃがれた声の持ち主、そう、ジェイソン・ディルです。
僕は心の中で「ディルだ」と叫びました。今までに日本に来た外タレ(外国人タレントスケーター)をスポットのアテンドや撮影を何回かしたことはありましたが、彼ほどオーラのある人はいませんでした。あともうひとつ僕を異常なまでに興奮させた要因としては、クイムが子供のように「おい、ジェイソン・ディルだよ! スゲー」とはしゃいでいたのです。
しばらく彼のスケートを見ていていると、普通のトリックでもひとつひとつの動作がスタイリッシュで絵になる男でした。彼よりトリッキーなスケーターはその場に沢山居ましたが、誰よりも輝いていました。そして、僕の中にある思いが生まれたのです。「彼を撮影してみたい」。フィルマーとして当然のことです。しかし、どうやって声をかけるべきか考えました。そして限られた時間の中で思いついたのは、クイムとパウロをダシに使うということです。言いかたが悪いですが、どうにかして自分の立場と状況をアピールしたかったのです。もう一度、クイムにラインを撮らないかと言うと、彼も待ってましたとばかりOKと答えました。たぶんクイムもディルに何かしらのアピールをしたかったのだと思います。お互いの利害が一致、クイムの撮影が一段落したあとに、「ジェイソン・ディル撮れるかな」と聞くと「分からないけど、聞いてみれば」と無理70%ぐらいの返事が返ってきました。