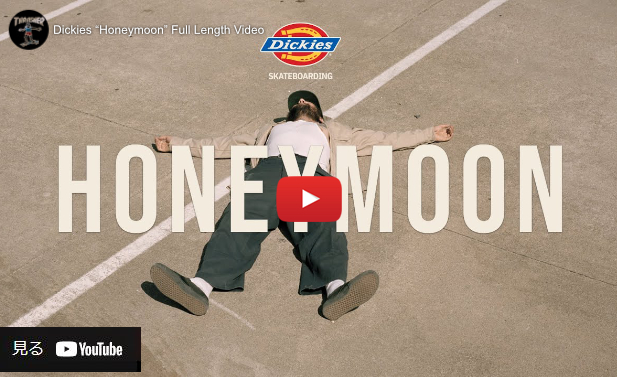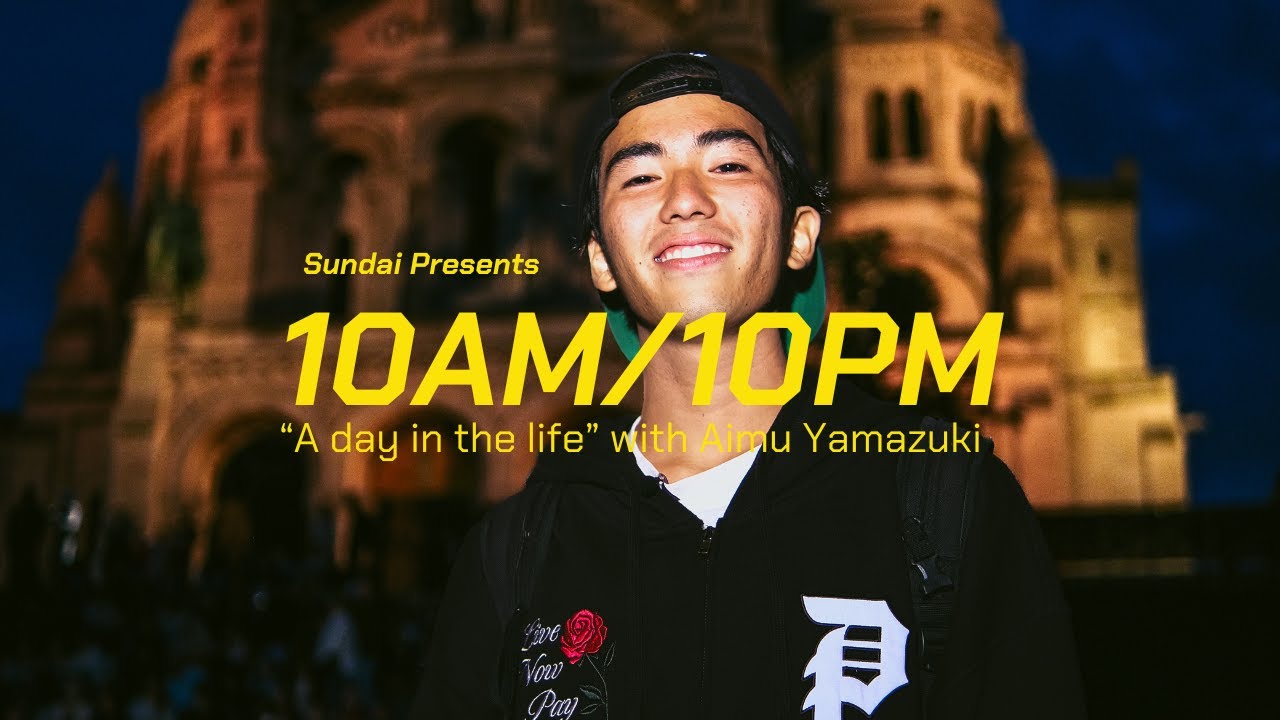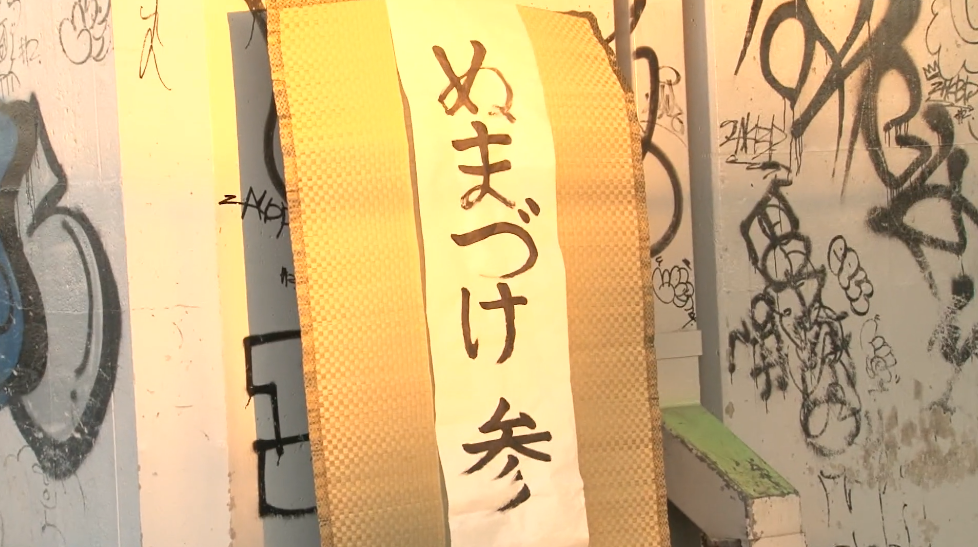30年前、たまたま読んだ映画史についての本を思い出す。そこに書かれていたステレオタイプについてのチャプターが印象的だった。例えばこんな感じだ。「ボストンは元々、アイリッシュ系の移民が多く、そういう人たちは俗に言うブルーワーカーと呼ばれる仕事に誇りを持って就いていた。それは警察官だったり、消防士だったり、ビルの建設業者だったりだ。そして、彼らのステレオタイプは、叱るときはゲンコツでぶん殴れ」だ。現代では、ゲンコツでぶん殴ることも、ブルーワーカーと呼ぶのも、アウトだろう。職業を断定的に記述することも厳しいところかもしれない。その本を読んで、WASP(ワスプ)という呼称も知った。ただね、個人的にはブルーワーカーっていうのは嫌いじゃない。というより、好きだったりする。なぜかというと、フットボールでブルーワーカーと言えば、無尽蔵のエンジン(体力)で攻守で走り回るボランチやサイドバックのプレーヤーを指す。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズやロイ・キーン、フランス代表でジダンを支えたクロード・マケレレといった、献身的かつテクニックも素晴らしかったハードワーカーでファンタジスタたち。バスケットボールでブルーワーカーと言えば、バスケを知らない人でも知ってるくらい日本でも人気だったデニス・ロッドマンや大都会NYCの顔だったチャールズ・オークリー、現役ならジョシュ・ハートといったまるでピットブルのようにボールに食らいつきフィジカルで圧倒するタフガイたちのことを指す。だから、ブルーワーカーというのはそういうちょっとやそっとのことではたじろがない、抜群の身体的センスとエナジーと自己のスタイルへの哲学を持って突き進んでいける人物だと思っている。それってかっこいいとも思っている。
スケーターもタフさやスタイルへのこだわりが強い。そして、誰のためでもなく自分超えのためにハードワークをいとわない。それって、ブルーワーカーとかぶるところがあったりするんじゃないかなって思う。そのくせ、メイクする写真や動画は、スポットの妙、スタイルやルックスの妙、非日常的な出来事の妙など、複合的ないい意味の違和感が満載で芸術的だったりする。そうなると、ブルーワーカーでクリエイティブでゲンコツでぶん殴るんじゃなくて強烈なスラムを食らってもへっちゃらなスケーターって、かっこよすぎると思ってしまう。そう思ってしまったまま、25年以上が経っている。前述の本を読んでからは30年が経っている。
そろそろ結びの時間かなと思っていたけれど、ここまでが前置きだった。ここで言いたいのは、ブルーワーカーをアパレルの部分(ユニフォーム的に?)で支えてきたのがワークウェアだ。今ではワークウェアというのは、文字通りの労働者のための作業着というエリアからどんどん進化と飛躍をして、カルチャーとファッションの一大コンテンツになっている。パリ・コレクションやロンドン・コレクションでトレンドの最前線をリードし続けるメゾンブランドだってワークウェアを取り込んでいるし、そういうブランドとコラボレーションをしたりもしている。いわば、ブルーワーカーじゃなくても労働者じゃなくてもワークウェアは着るしアイテムとして愛されているってこと。だから、正直Dickiesをワークウェアだと思ってもいなかった。自分が今よりもっと若かかった頃から、穿きやすくてシンプル、そして丈夫で何本持っててももっと欲しくなるパンツやウェアという存在だった。しかしよく考えてみると、Dickiesは1922年の創業以来、世界中(当然、ボストンのブルーワーカーも含まれるし、これまた当然でブルーワーカーだけじゃなくてすべて)の労働者のためにワークウェアをつくり続けてきた。そうして、ひたすらブレずにアップデートを繰り返していくうちに、「転んでも破れないぜ」「擦れても傷まないぜ」「ポッケにコイン入れても簡単には穴が空かないぜ」…という具合にスケーターたちにそのタフさが知れ渡るようになっていった。それが1990年代の話。自分が、がっつりとスケボーマガジンをつくるようになったのも同じ時期。だから、Dickiesといえばワークウェアというよりスケートやストリートでタフにやってる人間のザ・フォーマル(正装もしくはお洒落着)という認識だったのだ。だから、2020年代の今のDickiesの矢印は理にかなっていると思う。ワークウェアであり、(あえて確信犯的に書かせてもらおう)ブルーワーカーの味方であり、ブルーワーカーのようにタフであり芸術家のようにクリエイティブでもあるスケーターのフォーマルでもある。ストリートでプッシュするすべての人(と物語)にジ・アンサーできるブランドなんだと思う。ワークウェアと堂々と名乗りながら、スケーターをサポートし、スケーターに支持される、それがDickiesなんだなと改めて思った。そりゃあ、『Video Days』で衝撃的なビデオパートを残したガイ・マリアーノ、それは1991年の出来事。そんな彼とDickiesがしっくりハマるのは当たり前だろう。その頃からDickiesとスケートボードは相思相愛だったんだから。
─Senichiro Ozawa(Sb Skateboard Journal)