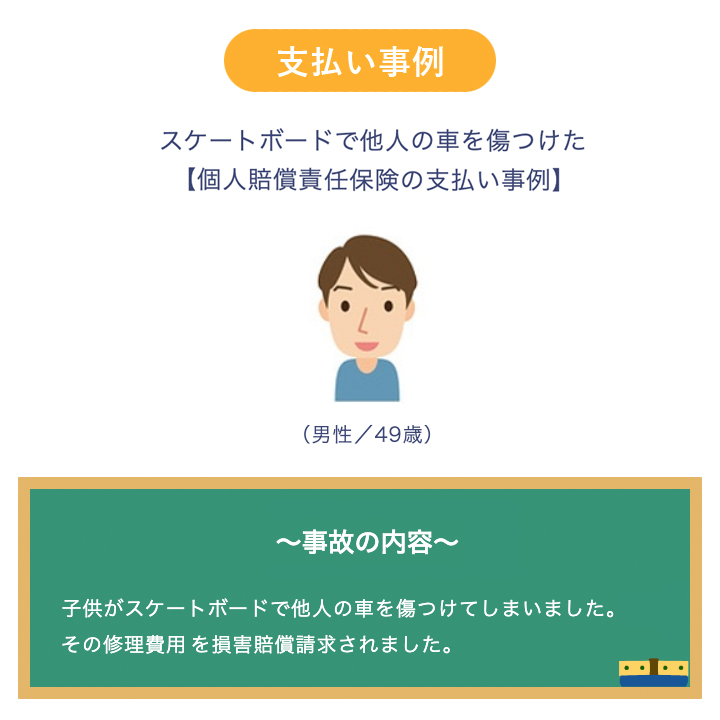拝啓、AIKI ARAKAKI!!!
カバーストーリー。
朝9時にショップBATSUに集合した。ショップによく来る若手のフィルマーふたりにも声をかけ、1カメ、2カメを確保。今日の主役アイキも入れて4人で車に乗り込んだ。現地で、ミスったときにデッキが流れていかないようにガードしてくれるスケーターがひとり合流することになっている。
撮影に向かうときは、余計なことはあまりしないように心がけている。するといえば、音楽を流しながらコーヒーを飲むことくらい。カメラバッグはひとつ。あとは三脚と小道具を大きなトートバッグにぶち込む。音楽は、アイキがすごい獲物をやりに行くときのお決まりとなったロッド・スチュワートの“Young Turks”をひたすら流す。この1曲しばり。延々リピート。ちなみにこれは、アイキが敬愛するenjoiのボス、ルイ・バレッタが『Bag of Suck』で使用していた曲だ。
現場に着いたのは10時30分だった。今日の撮影にタイムリミットはなかった。キックアウトされるか、散るか、メイクするかだ。快晴。秋めいた空気が少し冷たい。Tシャツでちょうどいい感じで、絶好のコンディションだった。獲物は、11段ステアにキンクを挟んでさらに10段のステアを足した細い丸レール。しかも、真ん中にレールが備え付けられている。仮にレール上でオフバランスになっても、フロントサイドにもバックサイドにも逃げ場がない。慰めの植え込みひとつさえない(血も涙もない)。どっちにスラムしても、氷のように冷たく痛い路面がウェルカムしてくる。ただ、地獄の何丁目かわからないハードさだとしても、そこでメイクする自分の姿をイメージをしてしまったら最後だ。スケーターもフォトグラファーも絵を残すことに夢中になる。それがファンキーDNAだ。
ちなみにここは、シャッターストリートの寂れた商店街の入り口。日向ぼっこをしているのは、野良猫と、ハンドレールが天国への階段に付いている優しい手すりに見えている老人たち。メロウでサイレント。そこに、脳内は“Young Turks”爆音ライブ中のアイキ。コントラストがたまらない。
アングルはもう決まっている。三脚を立てて、ストロボをセットした。ただでさえ交通量があるところなのに、今日は車の往来が一段と激しい。そのせいで、アイキは苦戦していた。自分が入りたいタイミングで思うようにレールに入れない。それでも、1発目で長いキンクレールの下の方までいった。「これはいける」とみんなが思ったはずだ。しかし、その後は、車の激しい往来に苦しめられることになる。アイキのアプローチには、彼特有のルーティンがある。まずはレールの前に立って、メイクまでのストーリーを描き、それから助走に入る。1トライごとにそれを繰り返す。しかし、今回はそのたびに車が来て、リセットされてしまう。それでも、なんとか入ったときにアバラを強打。したたり落ちる汗。ゆがむ顔。これは中古車販売のガリバーがどう低く見積もっても、とてつもなく高い下取り価格になる、いや、とてつもなくまずい痛みのはず。「これはダメかな」と思ってしまった。思わず、「無理しないで」と声をかけていた。しかし、アイキは「まだやります!」と揺るぎない。
顔は激痛で歪んでいるのに、アバラを強打したバッドイメージがまとわりつきそうになるのを振り払い、アイキのギアが上がった。30回目だった。ガツっという激しくて思いきりのいいオーリー、「これはレールにきれいに乗るぞ」と確信した瞬間、シャッターを切る。3つのストロボが日中シンクロを演出する。そのままファインダー越しにレールをグラインドするアイキを見つめる。この時間は一瞬のはずだが、とても長く感じた。そして、レールを流しきり、きれいに着地した。路面とソールでデッキをサンドするようにして抑え込む。メイクした。間髪入れずに、これはいつものクセだが、撮った写真のチェックをしてしまう。これはフィルムカメラではできなかったことだ。スケーターにしたら1発でメイクするのがすごいし、痛みやリスクも少ない。スポット的にも1発メイクの方がいろいろな理由でいいに決まっている。しかし、撮る側からすると、ほんとのほんとのところでは、何度か同じものを撮影できるとうれしい。なぜなら、最もカタチがよくて美しいスタイルの瞬間を捉えたいから。もちろん、1発メイクならば、こちらもその美しさを1発でメイクするのを心がけているのだけれど…。とにかく、メイクしたこの瞬間、うわーっと鳥肌が立つ。これまでにも何百回と味わっているこの感覚。だけど、一向に色褪せることはない。それどころか、どんどん、鳥肌が沸き立つゾクゾク感は濃くなっていく。これは、自分自身がスケボーでメイクしたときでも同じだと思ってはいるが、獲物をモノにしたスケーターのメイクを撮った瞬間はそれを上回っている気がしてもいる。
ちなみにストリートにおけるスケート撮影は、被写体にも撮った側にも優勝賞金が出るわけではない。木村伊兵衛賞や土門 拳賞のような写真賞の候補にもならない(今のところは笑)。そんなことはどうでもいい。ただただ、がんばって、がんばってメイクするスケーターにグッとくる。アイキがメイクしたときは、これにもルーティーンがあって、そこにいたメンバーみんなで獲物の上で抱き合って歓喜する。この光景は何度見てもいい。何度も見たい。
12時51分になっていた。ショップに戻って解散する。販売用のトラックをディスプレイしたラックの下に機材一式をしまう。余韻に浸りながら、メモリーカードをパソコンに落とし込みながら、ゆっくりと写真を眺めていく。ちゃんと撮れているか。ブレてないか。ストロボは飛んでいるか。少し緊張する。大丈夫だったとホッとする。それからは、「ヤバかったなあ、マジで」と呟きながら、何度もメイクした写真をチェックする。それからショップをオープンさせる。今日は14時オープンだ。
ショップは基本的には毎日オープンしてるけれど、その時間はまちまちで定時がない。いいスポットがあれば、スケーターからアプローチがあれば、そういう撮影があればどうしてもそれを優先してしまうからだ。ついさっきとてつもない獲物を撮ったばかりなのに、もう次の撮影のことを考えている。もっともっとスケーターを撮りたい。わかりきったことだが、自分の写真にはスケーターしか写っていない。自分にとって写真とはスケートグラビアのこと。スケーターと一緒に動いて写真を撮り続ける。それがやりたいことだし、それしかしたくない。スケート写真からはじまり、その後はいろいろなものを撮っていくプロフェッショナル・フォトグラファーが多いけど、自分は被写体がスケーターじゃないと意味がない。これが今回のヘッドライナー遠藤義明(49n)とSbとの特集後日談。
—Words & interview by SO(@sbskateboardjournal)