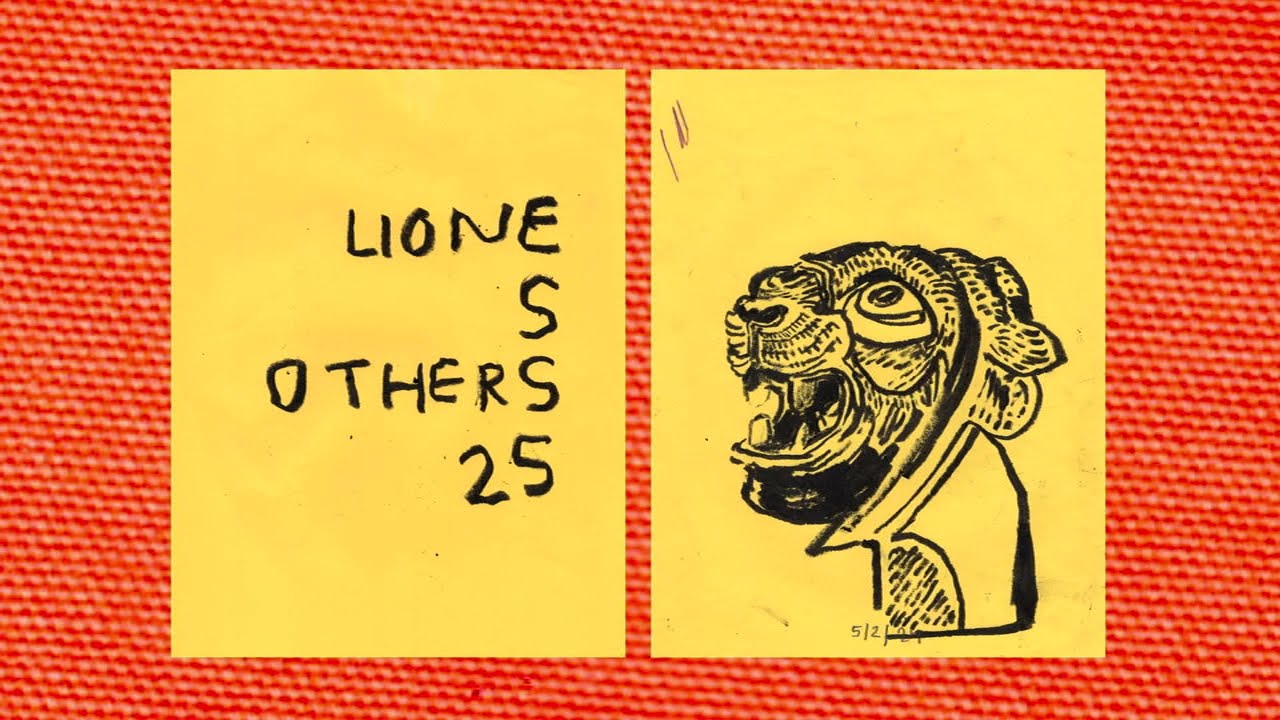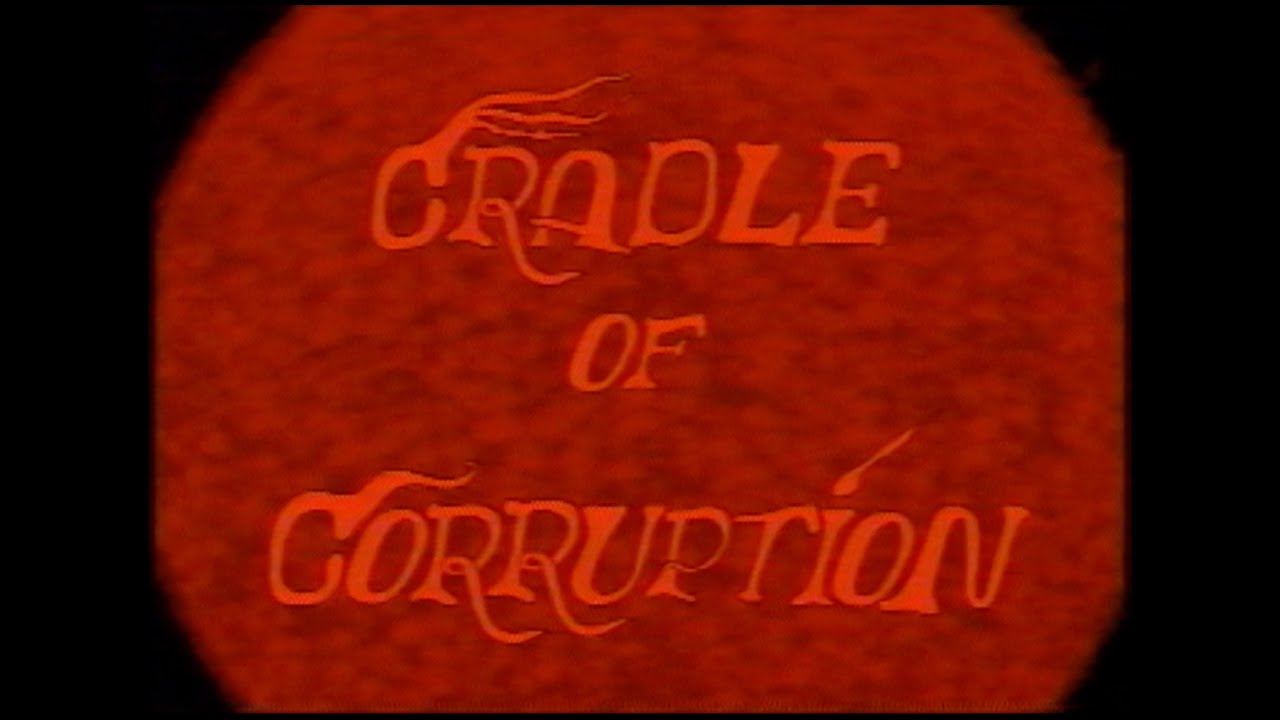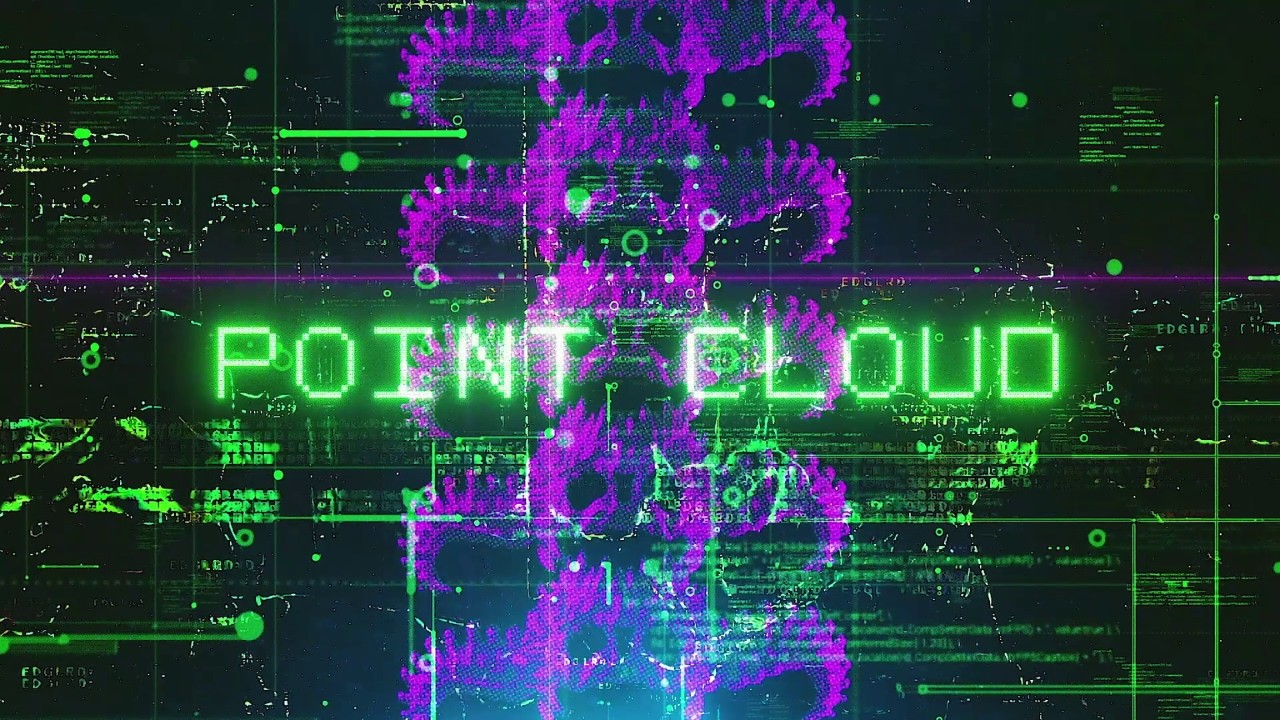ADIDAS SKATEBOARDINGのツアーで初来日を果たしたダン・マンシーナ。スケートボードが与えてくれたポジティブなマインドとエネルギー。目の病と向き合いながら再び手に入れたスケートライフ。
──DAN MANCINA

[ JAPANESE / ENGLISH ]
Photo_Junpei Ishikawa
Special thanks_adidas Skateboarding
VHSMAG(以下V): 出身地と現在のホームタウンは?
ダン・マンシーナ(以下D): ミシガン州出身で今もそこに住んでる。デトロイト郊外の小さな街。
V: スケートを始めたのは?
D: 7歳頃に適当にプッシュしながら始めた感じかな。従兄弟がスケーターだったんだ。まずはスノーボードにハマったんだけど、専門誌を読んでると夏に練習としてスケートすればいいと書いてあった。それでスケートにどっぷりハマった。13歳だった。
V: 13歳の頃にいずれ視力が低下することについて知ったんだよね?
D: そうだね。13歳で診断されたんだ。網膜色素変性症っていう病気。通称RP。遺伝性の病気なんだ。時間とともに視力が低下する病なんだけど、進行の速度には個人差がある。診断された当時は特に生活に影響はなかった。夜に見えにくく感じることはあったけどね、まずは暗視能力から低下していくから。だから夜になると病気の影響が多少あったけど、目の見える人と同じように生活してた。いずれ失明することについて考えることもあったけど、まだ現実味がなかったという感じかな。
V: 徐々に視力が低下していったんだね。
D: オレの場合はそう。兄が3人いるんだけど、その内のふたりもRPを発症してるんだ。オレより年上なわけだけど今も視力はある。だからこの病気がどんな影響を与えるかは人によって違うんだ。オレの場合は他にも目の疾患があったから視力の低下に拍車がかかったんだと思う。そして20代半ばで生活に支障をきたすほど病気が進行し始めた。車の運転ができなくなって、スケートも2年ほどやめるようになった。息子もいたからいろいろ大変だった。そうやって視力が低下していった。今は32歳なんだけど、もう何も見えない。
V: 数年前のインタビューでは光を感知することができるって言ってた。当時は5~10%ほど視力が残ってたんだよね?
D: そうなんだけど、今は完全に失明した状態。何も見えない。昨年の12月頃に残りの視力を失ったんだ。光や影を感知できる周辺視野が少し残ってたんだけど今はゼロ。でもそれでちょっと安心したっていうこともあるんだよ。というのも、もう毎月病院に行く必要がない。それまでは毎月医者に通って目に注射を打ってたから。安心したと同時に失明した状態でスケートする不安や恐怖もあった。でもここ数ヵ月で少し視力が残っていた頃よりスケートが上手くなった。次のパートの公開が待ち遠しい。
V: パートを撮ってるの?
D: もちろん。つねに撮ってるよ。
V: 20代の頃の話に戻りたいんだけど、視力を失い始めたときはどんな心境だったの?
D: 「ついに始まった」って感じ。ちょうど皿洗いしてるときに視力の低下を感じたんだ。そして2年の間に車を運転できる状態から誰かと一緒じゃなきゃ外を歩けないようになった。突然、盲目の世界に放り込まれた感じ。世の中との関わり合い方が急変した。そしていろんなことを覚え直さなければならなかった。自分が誰かもわからなくなった。当時はいろんな感情が交差していたよ。「オレは誰なんだ?」ってね。仕事はどうすればいいんだ? 子供をどうやって育てればいいんだ? どうやって生活すればいいんだ? そして白杖を使うオリエンテーション&モビリティという視覚障害者の訓練を通して徐々に自信を取り戻すことができた。それまでの自分を取り戻してできることからやるようになっていった。そうして視覚障害者だって充実した人生を送ることができるって実感することができた。目が見えなくたって人生を楽しむことができる。そして「視覚障害者にできること」を探すんじゃなくて、「オレがしたいこと」を探すようになったんだ。
V: じゃあ視力を失うまで準備をさほどしてなかったってわけ?
D: まあ、病気の進行がもっと遅いと思ってたからね。
V: 視力を失ったことで考え方はどう変わった?
D: 最初は現実を受け入れる努力をしながら嘆くしかなかった。そして次第に周りの対応に嫌気が差すようになっていった。今でもそうだけど。要は特別扱い。哀れみや同情。オレと会う人はみんな悲しそうだった。オレはみんなにハッピーでいてほしいのに。それが原因でインスタグラムに視覚障害者がやらないようなことをして動画を投稿するようになった。ダーツ、ビアポン、卓球。こういった動画でオレの「かわいそう」いうネガティブなイメージを払拭することができたんだ。たしかに今でも盲目であることを気にしたり不安になることもあるけどね。でもスケートボードのおかげでそういった状態から抜け出すことができるんだ。アイデンティティを確立させることができて自信を取り戻すことができる。同情されるんじゃなく、「スケーターなんだ? 好きなことができてるなんてクールじゃないか」って思ってもらいたい。現にオレが何をしてるか知るとみんな喜ぶし。「かわいそうに」から「好きなことしてるんだ」という考えに変わるんだ。
V: スケートをやめなかった理由は?
D: さっきも言ったけど2年ほどやめたことはあった。当時はスケートのことなんて考える余裕がなかったから。視力を失った頃はスケーターでも何でもなかった。でも今思えば例のインスタグラムの動画がきっかけでスケートをまた始められたのかな。スケートするには秋が一番好きなんだけど、ちょうどその季節にスケート用のボックスを作ったんだ。ただの暇つぶしだったんだけどね。そしてフロントボードを撮影したんだ。でも昔のようにスケートで満足なんてできないと思ってた。上手くなれるとも思ってなかったし、スケートをまた始めようという決定的な瞬間もなかった。ただボックスを作ったことでスケートするきっかけができただけ。でもその動画が好評だったんだ。トニー・ホーク・ファウンデーションのウェブサイトでもシェアされた。そうやってさらに動画を撮るようになっていったってわけ。
V: いいね。
D: でも周りの仲間は次々とスケートをやめてたから大変だった。一緒に滑れる仲間が誰もいなかったわけだから。だからフラットでひとりで滑るしかなかった。そうしてRed Bullの取材が入ってドキュメンタリーが公開されたんだ。それもJenkemのインタビューがきっかけだったんだけど、そういった企画を通してスケートコミュニティに舞い戻ることができた。そしてスケート仲間がまたできてスケーターとしての自分を取り戻すことができた。それからはまた四六時中スケートのことばかり考えてる。ジム・シーボーのような人がオレを支えてくれてデッキを送ってくれるのにも勇気づけられる。本当にありがたい。あんなに影響力があって昔から大好きだったスケーターやブランドがサポートしてくれたこともスケートを続けられる理由のひとつだったから。
V: 視力を失い始めた後はずっと杖を使ってスケートしてるの?
D: そうだね。当時はまだ影くらいは見えたから。スケートをまた始めたのがテニスコートだったんだけど、路面のコントラストがわかりやすいんだ。白いラインが引かれてるからね。ラインに沿ってまっすぐ進むことができたし、杖を使ってボックスの位置を知ることもできた。オレの視力ではボックスをはっきり見えないから。物を立体的に見ることすらできない。地面にボックスの絵が描かれてても気がつかないくらい。そういうわけで杖でボックスの位置を感知してテールを弾く。完全に視力を失った今は手でレッジを触らなくてはならない。杖で距離や感覚を掴んで実際に手で触る。レッジはそんな感じ。
V: 最新のスケート事情はフォローしてる?
D: まったくしてない。
V: でも目が見えた頃の記憶があるよね。
D: そう。だから'90年代や'00年代初期で時代が止まってるんだ。『In Bloom』といったTWSの作品を観て育ったから。最新情報はまたくフォローできてない。今回のようにツアーに出て初めて最新情報がわかる感じかな。近頃のスケーターのスキルはハンパないよね。ツアー中にヤバい撮影の現場に立ち会えるのはうれしい。
V: ちなみにダンのパートも最高だったよ。
D: ありがとう。
V: 今は視覚障害を持つ子供たちの支援をしてるんだよね?
D: できる範囲でね。視覚障害を持つ子供たちと会って、彼らが普段しないようなスケートについて教えてあげたいと思ってる。視覚障害者は「普通」とされる子供たちと比べてチャンスが限られてるから。通常だったら経験できないスケートに触れるきっかけを作ってあげられたらうれしい。でも彼らの親を説得するのが大変なんだ。視覚障害者の親にスケートの話をすると「無理だ」って思う人が大半だから。だから「何事もできないなんて思う必要はない」って思ってもらえる見本になりたい。その気になれば何でもできるってことを知ってもらいたい。子供は障害を持ってても持ってなくてもみんな同じ。ビデオゲームが好きな子もいれば、スケートをしたい子もいる。チャンスを与えることが大切なんだ。そこから何かが生まれればと思う。スケートを始めた頃は視覚障害を持つスケーターなんてほとんどいなかったけど、今じゃ世界中に何人もいるからね。
V: 視覚障害者のためのスケートパークを作りたいとも言ってたよね。
D: Keep Pushing Inc.っていう非営利団体を運営してるんだけど、そこを通してスケートパークを作ろうとしてるんだ。セクションの場所がわかるようにスピーカーを内蔵して音を出したり、地面を明るい色にしてセクションを暗く塗ったり、コーピングやエッジにLEDライトをつけたり、天井から紐とかがぶら下がってたり。最初は視覚障害者だけに向けたパーク建設を考えてた。でも今はいろんなライダーが使えるパークがいいと思ってる。たとえば車椅子のWCMXとか。万人に向けたユニバーサルデザイン。これがオレの夢。そろそろ実現させたいね。
V: 是非実現してほしい。ではadidasからサポートされるようになった経緯は?
D: すべてはポール・シャイアのおかげ。何年も前からBusenitzを買って履いてたんだけど、インスタグラムで例の動画を上げてたらポールからDMが届いたんだ。それがすべての始まり。最高のクルーの一員になれてうれしいよ。
V: そしてツアーで日本にいるわけだからね。
D: クレイジーな体験だよ。日本に行くっていう子供の頃の夢が32歳になってやっと叶ったんだ。
V: ではこれからの人生で成し遂げたいことは?
D: スケートでやりたいことがたくさんある。ハンドレールは絶対にメイクしたい。やりたいことは日々増えている。そういった意味では普通のスケーターと変わらない。あとはパークを作ることができれば最高。それ以外はこの先もずっと家族を支えていければと思う。息子の手本になれる父親でありたい。そうやってプッシュし続けたい。
V: では最後に悩みを抱えて苦しんでる人たちに言葉をかけるとしたら?
D: そうだね。それについてはいつも考えてる。オレの場合は失明したことで物事の見方が変わって人生を楽しむことができるようになった。今のオレのはいい感じだと思うんだ。どん底に落ちてもおかしくないからね。オレが言えることといえば、探すのをやめないこと。オレも自分自身や人生を取り戻そうと何かを探し続けてきた。本当に行きたい学校と出会うまでに学位もふたつ取ったし。気に入ると思った職に就いても結局自分に合わなかったこともあった。大切なのはずっと探し続けること。何にでもトライすること。結果的に上手くいかなくても前進さえしてれば…オレの場合は上手くいった。だから止まらなければ大丈夫。専念できることを探すんだ。オレにとってそれがスケートだった。裁縫でも何でもいい。ありふれた日常を離れて自分を表現できる何かを見つけてほしい。
Dan mancina
ミシガン州出身。13歳で先天性の網膜色素変性症と診断され20代で視力を失い始める。現在はadidas SkateboardingやRealのライダーとして活動しながら、身体障害者に向けたユニバーサルなスケートパーク建設の実現に向けて準備を進めている。
@danthemancina