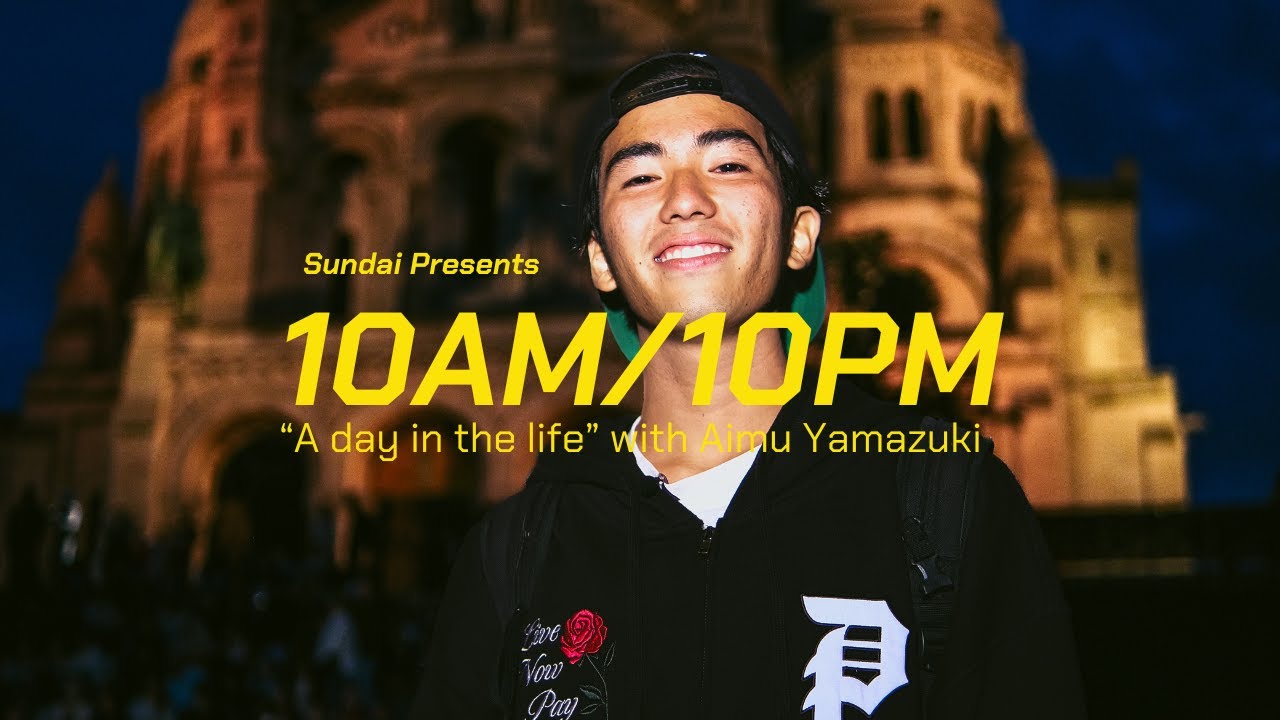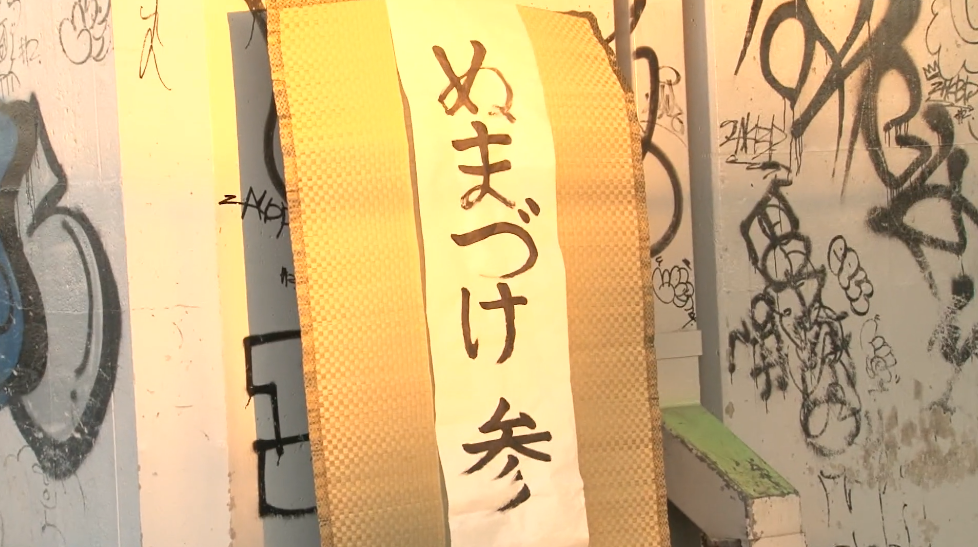デザイン性の高い誌面とセンス良すぎるスケートの見せ方でファッション業界やメディア関係者を夢中にさせたスケートマガジン、Dank。最新号のリリース記念に日本を訪れた編集長アイリクに会うことができた。
Interview by Katsushige Ichihashi Photos courtesy of Dank magazine
これまでスケートシーンの勢力図において完全にノーマークだったノルウェーのオスロから登場したスケートマガジンのDankは、その後の若い世代の北欧スケーターの台頭ぶりを予見するかのように毎号地元ノルウェーのスケーターもきっちりと特集しつつ、ヨーロッパをはじめ世界各国に生まれたインディペンデントなブランドにも積極的にコミットして独自のネットワークを形成していった。一度、Dankを手にした人にはわかってもらえるだろうが文字通り、これまでにはなかった感触のスケートマガジンなのだ。創刊号から完成していたそのスタイルを生み出したのは編集長のアイリク・トローアヴィク、フォトグラファーにしてデザイナーのヨルン・オーゴールド、そして副編集長にしてノルウェーのスケートシーンの重要人物やスケートボーディングの歴史にまつわるコラムを手がけることも多いアクセル・オバスコットの3人。最新号の発売記念パーティを開催するために日本を訪れていた彼らに会い、編集長のアイリクに話を伺うチャンスに恵まれた。
VHSMAG(以下V): 3人はどうやって出会ったのでしょうか?
アイリク・トローアヴィク(以下E): 僕はオスロ出身なんだけど、アクセルとヨルンはオスロから1時間ほど離れた小さな街、ハーマルの出身なんだ。大学生の頃にアクセルのルームメイトと知り合ったり、それこそ彼がオスロに引っ越してくる前からもハーマルの人で彼の親友とも知り合いだった。ほら、10代の頃にスポンサーがつくようなスケーターってまるでロック・スターみたいな存在だろ? その親友もそういう連中のひとりで有名人みたいなものだったんだ。アクセルはそのスケーターの友達と一緒にスケートをするためにオスロに移ってきた。そして一緒に滑りにいったときにすぐに意気投合し、そこからずっと付き合いが続いている。ヨルンともそのグループを通して知り合った。ハーマルのスケートシーンはとにかくやばくてノルウェーでも1、2を争う存在なんだ。若い子はサッカーをするかスケートするか、ふたつにひとつみたいなところでね。で、当然みんなスケートボードの方にいっちゃう。全員スケーターみたいなものだからうまい子もたくさん出てくるんだよ。
V: なぜハーマルのシーンがそれだけ盛り上がっているのでしょうか?
E: 理由はさっぱりわからない(笑)。とにかく濃いシーンで、他になにもすることがないからじゃないかな。滑るしかないから必然的にうまくなっていくんだろうね。いいパークもあるし、みんながお互いを高め合っていくような関係になっている。レールのスポットもひとつくらいしかないけど、みんなでとにかくそこを攻めていってどんどん技術的に進歩しているような感じだよ。ハーマル出身のスケーターとよく滑るようになったときにヨルンにも出会った。彼はフォトグラファーとかフィルマー役でね。オスロでよくつるむようになったんだ。
V: Dankはスケートマガジンを作りたくて3人で始めたのですか? あるいは3人でなにかを作ろうとして、結果的にスケートマガジンになったでしょうか?
E: 2009年、僕がバンクーバーにいた頃によく行っていたスケートショップのAntisocialにジンやインディペンデントなスケートマガジンのコレクションがそれこそ本棚いっぱいにあって、それにすごく影響を受けたんだ。あとはColorというカナダのスケート〜カルチャー系のすごくいい雑誌があってね。はじめて手にとったとき「やばい。見た目も内容もすごすぎる」て思ったよ。当時のオスロで手に入った地元の雑誌とは大違いだった。ノルウェーにはスケートマガジンがなくて、ちょっとだけスケートも取り上げるスノーボードの雑誌しかなかった。それもひどいレベルの写真と意味のないというか、適当にでっち上げたような記事しか載せていなくてね。僕は18歳のときからライターとしての仕事もしていて、アクセルもスケートボード関係のウェブでライターをやっていた。まぁ、あまり面白くはなかったみたいだけど。ヨルンはすでにデザイナーの仕事もやっていたからアクセルにカナダからスカイプかなにかで「自分たちでもっといいスケートマガジンを作ろうよ」と話を持ちかけていたのをおぼえているよ。

V: 自分たちがもっと共感できるものを作りたかったのですね。
E: そう、自分たちがスケートボーディングのどこが好きなのかを表現したかった。なにせオスロには同じ気持ちを共有していると思えるような雑誌は存在しなかったからね。最初はLowcardみたいな、ローファイで典型的なスケートジンを作ろうとした。オスロのスケーターとはほぼ全員、顔見知りだからきっとみんなの面白いインタビューを集められるだろうと思ってね。でもある日、ヨルンが「なにか作るならもっと良質で、世の中に広く認めてもらえるようなものを作るべきだ」といって。
V: まさにそこを聞きたかったのです。それこそ誌面のサイズからマットな紙質まで、これまでに存在していたどのスケートマガジンとも違うこのDankのスタイルにいきついた過程に興味があります。ましてや最初のアイデアではローファイなジンだったとは!?
E: いまのスタイルにいきついたのはやっぱりヨルンの言葉がきっかけだったね。2010年の終わり頃、ノルウェーの出版社で働く人のインタビューで「あえてこのインターネット時代に良質の印刷物を作ることの意義」について話しているインタビューを読んで、ネットなんて二の次にして、とにかく良質な印刷で雑誌を作ろうという思いに至った。スケートコンテストの結果やツアーレポートみたいな時事的な内容ではなく、いつ本棚から取り出しても楽しんでもらえるような、時間の制限を超えた内容にしたかった。そして当然、紙質にもこだわったよ。だってせっかく印刷するなら紙にもこだわらなくちゃ! まぁ、そこはヨルンの専門でもあったんだけど。ヨルンは本のこととなるとオタク級で、彼にとってDankは雑誌というよりも「本」なんじゃないかな。当時はフランスのSomaやドイツのAnzeigeberlin Informationが大好きで、イギリスのGreyもちょうど出始めだったかな。みんなそれぞれに独自の美意識をもっていたわけだけど、僕たちはもっと洗練された、それこそスケートボーディング以外のジャンルからも積極的に良いものを取り入れたスタイルを打ち出したかったんだ。3人ともさまざまな分野に入れ込んでいるからね。そしてただの雑誌として読み捨てられるようなものではなく「残る」ものを作りたかった。見た目も良くて、それこそ匂いも良くて、スケートボーディングの世界ではまだ誰もやっていない新しいものを作りたかったんだ。
V: トリックやスケーターのアップではなく、かなり引いたロングショットを多用してスポットや街並みも見せて誌面上に構成する写真の世界観もすごく好きです。この質問はヨルンにすべきかもしれませんが、意識的にそういうテイストや構図の写真を選んで、トリックの種類よりもスケーターや街のキャラクターなどを見せようとしているのですか? 個人的にはそうやってトリックに肉迫するよりもそのまわりにある時間や空気感を見せるスケートビデオやスケートフォトは実にヨーロッパっぽいなと思います。
E: Dankがまわりにあったものに対するリアクションから始まったのが大きかったと思う。いまはもうそういうこだわりはなくなったけど、始めた当初はとにかくスケート界でやり尽くされたような典型パターンからできるだけ距離を置こうとしていた。だからロングショットにしてもヴィジュアルの美しさも大きな要素だけど自分たちとしては階段に寝転んでレールの下から魚眼レンズで撮ったような写真は使いたくなかった、というのが理由だったとも言える。それにヨルンはDank以前からもよくロングショットで撮っていたんだよね。彼が自作のスケートビデオの上映会用に作ったポスターなんかも建築写真かと思うほど美しい構図の、望遠で撮った写真を使っていたよ。だからDankの誌面もまずはそこから始めたわけだけど、とくに意識的にそういったロングショットで街を見せようとしていたわけでもないんだ。だって読者は同じノルウェー人だけだろうと思って1号目を作ったわけで。ところがしばらくしていろんな国の人たちから反応をもらうようになって、はじめてDankがノルウェーのスポットをみんなに紹介していることに気付かされたんだ。自分たちにとってはごく当たり前の風景が他の人にとっては珍しいものに写るんだから面白いよね。スケーターならガードレールの形ひとつにも注目する。でもそうやってスポットの姿とスケートボーディングが街の一部になっている情景を見せられるのはうれしいことだと思う。

V: Dankに登場するさまざまなアーティストや3人以外にも定期的に寄稿するメンバーの人選も秀逸ですが、さらにいろんな人に参加してもらいたいですか?
E: いつだって参加メンバーを募集しているよ。ただ、やっぱり限られた予算で動いているという現状があって、正直、ギャラを払える状態ではないんだよね。僕もライターだからよくわかるんだけど「ギャラ無しでもいいかな?」と言わなきゃいけない状況ってとてもじゃないけど理想的とは言えない。ラッキーなことに面白い仕事をしている友達がたくさんいてくれるおかげでなんとかその範囲内でメンバーを構成できているんだけど、もっとたくさんの人に参加してもらえたら嬉しいな。Dankがちょっと知られるようになってからは実際に参加したいというメールもどんどん届くようになったよ。
V: 創刊は2011年でもうすぐ4年になりますが、この4年間はどうでしたか? 創刊当初で一番大変だったこと、そしていま現在、一番大変なことと言えばなんでしょう?
E: いつだってお金が一番大変だよ。創刊の頃は「さぁ、雑誌でも作っちゃおうぜ! なんとでもなるでしょ…」という感じだったんだけど、実際にはなにもわかってなかったんだよね。もちろん僕にはライターやデザイナーとしての経験はあったけど、雑誌作りに関してはやっぱり素人だったことを実感させられた。だから実際にやっていく中でたくさん学んだよ。失敗もあれば幸運に恵まれたこともあった。でもちょうど世の中の景気がどんどん悪くなっていく時期と重なったせいもあってDankの財政面のやりくりも難しくなり本当に大変だった。もちろん、雑誌作りのクリエイティブな側面が大好きだからDankを作ったわけだけど、それには運営やビジネス面での膨大な仕事もついてまわるんだよね。理想を言えばそっち側ももっとうまくやれるはずだけど、でもいい状況だとも思う。いろんな人がDankに参加してくれているし、その中には自分たちが大ファンな人もいたりして、さらにそういう人たちが参加してくれたおかげでDankの存在が広まってくれたし。
V: グレッグ・ハントも何度か登場していますよね。
E: 彼はあるときオスロでやったDankの発刊記念パーティにふらりと現れて、それ以来のつきあいなんだ。彼はDankをすごく気に入ってくれていて、いろいろとサポートしてくれている。ポンタス(・アルヴ)やCrailtapのベン・コーレンなんかもサポートしてくれているし、面白い状況だよね。いつの間にかDankのまわりにすごいネットワークができあがっているんだよ。世界の果てのノルウェーの小さな雑誌が「う〜ん、次の号にはジェリー・スーの写真の特集なんかどうだろう? ちょっとしたインタビューも欲しいかな」なんて言ってて、1週間後には実現しちゃってるだから! もちろん、なんでもかんでも簡単に実現するわけじゃないけど、無条件に「いいよ、参加したい」と言ってもらえるだなんてね。創刊当初にはこんな状況になるとは夢にも思っていなかったから正直怖くなる瞬間もある。でも、こんな小さな雑誌でもいろんな人たちに出会えて、一緒に仕事したいと言ってもらえるんだもの。最高だよ。

V: Dankを通じて自分たちのヒーローに会えるのは楽しいですか?
E: 最高だよ。雑誌作りの中でも一番の瞬間だね。たとえばこんなこともあった…。2号目を作っていた頃に僕は友達の引っ越しを手伝うことになってノルウェーからオランダを通ってベルギーのアントワープまで車で走ったんだけど、ちょうどそのときにGRAVISの写真展が開催されていて、ジェイク・ジョンソンをインタビューするチャンスに恵まれたんだ! もう最高だったよ。そんな巡り合わせがあるなんてさ…。あれはやばかった。
V: 年に2冊というスローなペースながらも同じ人を複数回数とりあげることもありますよね? 創刊号に登場したポンタス・アルヴやニック・ジェンセンはそれぞれ自分たちのスケートカンパニーを立ち上げてから再登場しています。
E: ポンタスに関しては単純に自分たちが彼の大ファンなのが大きいかな。それに最初にインタビューしたときに彼が自分の小さなブランドを立ち上げたいことを告白してくれたから実際にPolar Skate Co.が始動したときはワクワクしたよ。当時はポンタスがいまほどいろんなメディアにとりあげられないというか、まだまだアングラな存在だったから、僕たちでよければまた誌面に登場してもらいたかった。ニック・ジェンセンにしてもそうだね。まぁ、創刊号はやっぱり気合いが入っていたというか、とにかく好きなものをすべてカバーしようという意気込みが強かった。でも発行部数が少なかったし、内容はすべてノルウェー語だったこともあってそれほど多くの人に見てもらえなかった気もしたから彼らをもう一度、別のアングルから取り上げるのもありなんじゃないかと思って。
V: なるほど。3人はみんな近所に住んでいるの? Dankの編集部はどういう風に機能しているのでしょうか。
E: いや、近くに住んでいるというわけではないけど、オスロに事務所があって、そこに僕とヨルンと、あと『Perry』という短編映像を撮ったカスパーの机があって普段のフリーランスの仕事もそこでやっているからヨルンとはDankの作業に関係なく毎日、顔を合わせるよ。Dankの編集作業に入るとそこに篭もる感じだけど、誌面にはできるだけ新鮮な記事を載せたいと思っているからいつも作業自体は短期間に一気に仕上げるようにしている。
V: 1年に2冊というペースは最初から決めていたことでしたか?
E: 創刊当時はまだ学生だったからそれ以上のペースでは出せなかった、というのが実情かな。まぁ、お金の問題もありつつ、自分たちはあえてこういうスローなペースでやらせてもらいます、という意思表示みたいなものでもあったけど。
V: と言うのは、その年の後半に出る号はたいていページ数がすこし少なめになることに気付きまして、記事が一定のページ数になるまで待って年をまたぐよりはページが少なくても年に2冊というペースを絶対に崩さないようにしているのかな? と思った次第なのです。
E: それは春の方がスケートの撮影がしやすいせいもあるね。
V: 夏ではなく、春ですか? 意外です。てっきり北欧の人たちは貴重な夏を謳歌するものだと思っていたので。
E: たしかに夏を最大限に楽しむけど、必ずしも地元やオスロみたいな都市で、というわけではないんだよ。僕やヨルンもサマージョブをやったりするし、みんなオスロからいなくなっちゃうから撮影を企画しようにも人が集まらない。あとやっぱり春は長い冬があけた後にまたスケートできるようになったスケーターたちのやる気がハンパ無いんだよ。
V: オスロのスケートシーズンはいつから始まるのですか?
E: まだまだ寒いんだけど3月くらいかな。あと寒さや雪に加えて厄介なのが滑り止め用に撒かれる砂利なんだよ。雪がすぐに凍って滑りやすくなるから市の職員が初雪のあとから撒き出すんだ。だから春先にスケートする場合は雪用のショベルと砂利用のほうきが必需品になる。4月か5月まではあちこちに砂利が残っていて滑ることができる場所が限定されるほど。でも、その年の2冊目が1冊目よりもページ数が少ないことがあるのは面白い指摘だね。雑誌を作るのはものすごく楽しいからページ数を稼ぐのに苦労したことは一度もないよ。書くことはいくらでも見つかる。逆にいつだって泣く泣くカットしてるくらいさ。やりたいことはいくらでもあるから自分の思い通りに作ったら簡単に200ページを越えると思う。それだともっと多くの人にも参加してもらえて、きっと楽しいんだろうなぁ。その分厚い雑誌を発送するのは大変そうだけど(笑)。そしてその予算さえあればなぁ…。
V: 以前のインタビューではDankが地元よりもノルウェー以外の国から注目を集めているように思えると発言されていましたが、その状況に変化はありましたか? いまは地元からの注目も感じますか?
E: ノルウェーは不思議な国で、Dankはスケート業界以外の人たちに、たとえば雑誌や印刷メディアの関係者にすごく支持されているんだよ。ただ、僕たちが注目するヨーロッパのスケート・シーンの動き、各国にMagentaのような小さなブランドが生まれて活躍している動きが多くの人に認知され始めているのは確かだから、そういった人たちがいずれDankのことも気付いてくれるはずだと思っているよ。ただいつも苦労するのがキッズたちのハートをつかむことだね。マーケティングなんてできないからそういった若い層はまだまだDankのことを知らないままなんだよね。
V: ノルウェーにも新しいスケートカンパニーが登場しましたか?
E: 残念ながら新しい動きはない。Classic Skateboardsという名前のブランドが小さいながらもやばい動きを見せているけど。Menace Skateboardみたいなテイストで、’90年代のフィーリングとかHip-Hopのヴァイブを全面に押し出したクールなブランド。彼らはつねにアンダーグラウンドな存在であり続けようとしていて、プロダクツも店舗販売しないほどなんだ。ノルウェーで最大手のスケート系のチェーン店に販売させてほしいと言われたときも答えは「ノー」だった。彼らの商品を買うにはストリートで関係者をつかまえて直接買うしかないんだよ。Championのロゴへのオマージュだったデッキを4号のProduktsiderのコーナーで紹介したこともあったよ。彼らはいい仕事をしてるけど、他にはなかなか新しい動きは出てこないね。
V: そうですか。それはちょっと残念ですね。では、今回の「日本ツアー」の企画はどうやって生まれたのでしょうか?
E: 以前にDankの流通を出がけてくれた敦史(※Twelvebooks 濱中敦史)のすすめだったかな。2012年にオスロでやったイベントに彼も来てくれて、東京でも絶対にやるべきだと言ってくれて。僕も2007年に一度日本に来たことがあったからまたここに戻ってきたい気持ちもあったし、東京にはDankを販売してくれているショップがいくつかあるし、少なからず読者も存在するだろうから、そんな無茶な企画が実現できたら面白いかなと思って。

V: 日本に来るのは2度目だったんですね。先日のイベントには創刊号にも登場していたノルウェー人のスケーター、エイリク・バロにも会ってびっくりしました。しかも彼はいま日本に住んでいるとのことで。日本とノルウェーにはそんな強い結びつきといいますか、深い関係があるのですか? 正直、自分にとってはノルウェーはそこまで身近な存在とは思えないのですが。
E: そこは僕も正直よくわからないけど、やっぱり東京という街がみんなの興味を引くんじゃないかな。まず何と言ってもオスロとはまったく違う、未来都市のような街だし、きっとみんな映画の『ロスト・イン・トランスレーション』を観ているだろうし、スケーターなら宮城 豪やいろんな日本のスケートビデオも観ているはずだし、とにかく興味を引きつけられる存在なんだろうね。僕の場合はずっと東京に興味を持っていたから来たくてたまらなかったよ。そして実際に来てみたらやっぱり最高だったね。世界で一番好きな街かも。
V: Dankは日本のファッション雑誌やカルチャー誌にも何度か登場しているのでてっきり日本とは縁深いのかと思っていましたが。
E: それは僕の友達がVacantの小鷹直紀の知り合いだったおかげだと思う。彼が僕たちをPopeyeやEyescreamに紹介してくれたんだ。でも今回、日本に来ることができたおかげで実際にいろんな人に出会い、知り合えたよ!
V: では、この先のプランについて聞かせてください。先日『Perry』という短編映像も発表しましたが、雑誌というくくりを越えた活動、あるいはスケートボーディング以外のジャンルで何かプロジェクトの予定などありますか?
E: 実はいろんなプランとそれこそ具体的な話もいくつかもらってはいるんだけど、形になるのはまだ先かな。アクセルはかなり忙しいから僕とヨルンでやることになると思う。かれこれふたりでいろいろとやってきたしね。これも本当にDankのおかげだね。Dankは僕らにいろんな扉を開けてくれたよ。あとは以前にTシャツを作ったりしたけど、またいろんな種類のものを作りたいね。ただ、これもまた僕らが「仕事」の合間にすべてを手がけているせいでなかなか思い通りに動けないんだ。なんだかすべてがサイドプロジェクトみたいな状態でね。でも楽しいよ。
V: Dankはどれだけ続けたいですか?
E: もちろん続けたいけど「どれだけ?」と聞かれると困るね。2年前にQuartersnacksに同じような質問を受けたときは「楽しい間は続ける」と答えたはずだけど…。
V: そしていまも楽しい、と。
E: うん、楽しいね。ビジネス的な側面はそこまで楽しくないけど(笑)。雑誌を作るのは最高さ。そして東京まで来ることができて、この前の土曜日のパーティにあれだけの人が集まってくれたのもただただ素晴らしいとしか言いようがない。そういう経験は本当に最高。今年はいろんな経験ができて、楽しい1年だった。これまでで一番楽しい1年になったかも。Dankでは利益をあげることはできないけど、自分たちの時間はたくさんつぎ込んできた。これはフリーランスの仕事で稼いでいるおかげで機能してるシステムなんだけど、もしもいつかフルタイムの仕事についたとしたらどうなるかな…。ま、それはそのときに考えるよ。
V: 3人のうち、ひとりでも辞めざるをえない場合は…。
E: 本当に小さなチームだからヨルンやアクセル抜きではとてもじゃないけどやっていけないよ。逆もまたしかり、じゃないかな。だからもしも誰かが抜けるとなったら終わりだと思う。でも現段階ではなにも決まっていないし、これからもDankを作り続けるつもりでいるよ。まぁ、ただのスケートボーディングのファンやライターでいたいときにビジネスマンにもならなきゃいけないのは変な気持ちなんだけどね。
V: これまでスケートボーディングが他の分野、アートや写真、ファッションなどに与える影響については幾度となく語られてきたが、こうして出版の分野において類まれな才能を持った若者たちがスケートボーディングにこれだけのインパクトを与えることを一体誰が想像しえただろうか? 「何を大げさな」と思うあなたはきっとまだDankを手に取ったことがないにちがいない。是非そのチャンスに身を委ねてみてもらいたい。
![]()

東京に着いた初日の夜。風邪をひいちゃったアクセルは地下鉄でみんなに風邪を移さないようにマスクを購入した。えらい。その夜、渋谷をブラブラしてヨルンはゲーム機で鮭フライにしか見えないような動物のぬいぐるみをゲットしようと必死だった。楽しかった。

こちらもアクセル。初の本格的な温泉に大興奮。いま東京に住んでる友達のアイリク・バロがろくに説明もせずに連れてきてくれたんだけど、僕らは大満足。ビールを飲んだり、ちょっとおいしいものをつまんだり、その後に他の男と一緒に裸になったりと楽しい場所だった。

東京駅の目の前にあったやばいスポット。すぐに自転車に乗った警察官に止められちゃったけど、なかなかいいセッションだった。周辺もいろいろと滑ってみたけど楽しいスポットがあちこちにあったよ。

オスロの地下鉄じゃこんな看板は絶対にお目にかかれないよ。

渋谷のJBS Barを探してる間にみつけた小さなレール。協同作業的な50-50向けの物件だね。

箱根に日帰り旅行に行ったんだけど、最高だった! 少し歩いてからケーブルカーで箱根山に登って、まさに観光って感じ。写真は硫黄のにおいに慣れようとしてるアイリクとアクセル。クールな場所だったなぁ。


雨が強くなってきたけど、大丈夫。だって見たこともないようなおやつがいっぱいあったから。温泉卵はまさにドープって感じで、お餅の方はQuartersnacksのロゴみたいだったからそれだけで大興奮だった。

東京に戻った僕らは築地で寿司としゃれこんだ。冒険してみたかったアクセルはアイリク・バロの助け無しに日本語のメニューから適当に注文してみることに。結果はサバと何かの貝、そして馬肉(僕たちにとっては超珍しい食べ物)だった。でもおいしかったみたい。まさに寿司サプライズだね。

Sexy Zoneは僕たちのお気に入りのJ-Popグループなんだ。早くヨーロッパもツアーしてほしい。

今回行った中でも最高に変わった場所かも。日本に来る数週間前にインスタグラムにセルフィをあげていた友達がいたんだけど、それが梟カフェだったんだ。調べてみると本当にそういうお店が存在する、ということで行ってみた。2000円払ってお店に入り、コーヒーを1杯と人懐っこい梟たちに会える権利にありつける。驚きのコンセプトだね。

六本木の森美術館もかなり良かった。展望台からは富士山まで見えたよ。

そして日光にも行ったよ。素敵なところだったけど、結構さびれてたなぁ。世界遺産の東照宮を見てまわったり、ツイン・ピークスに出てきそうなホステルに泊まったり、猿も何匹か見たよ。なかなかの1泊旅行だった。

1時間以上、山の中に入った場所にあった湯本温泉の足湯。僕たちが着いたときにちょうど地元の親切なおじさんが足を温めていたところだった。閉まっているところも多い時間帯だったけど、開いているところがあって嬉しかったよ。


東京に戻ってからもおいしいものにありついた。これはパンケーキ・エッグベネディクト(こんな食べ物があるなんて知らなかったよ)。そしてもうノルウェーに帰る頃になっちゃった。2週間なんてあっという間だね。早くまた日本に来たいよ!
Eirik Traavik
A young skateboarder and skillfull journalist/editor from Oslo, Norway. He started Dank in 2011, a magazine in which everyone, from Greg Hunt to your favorite fashion mag’s editor, falls in love.
Eirik Traavik
ノルウェー、オスロ出身。学生時代からフリーランスのライターとしても活躍し、2011年にスケート仲間3人でDankを創刊。そのセンスの良さはグレッグ・ハントといったコアなスケート業界人からファッション業界人まであらゆる人のハートをいとめる。