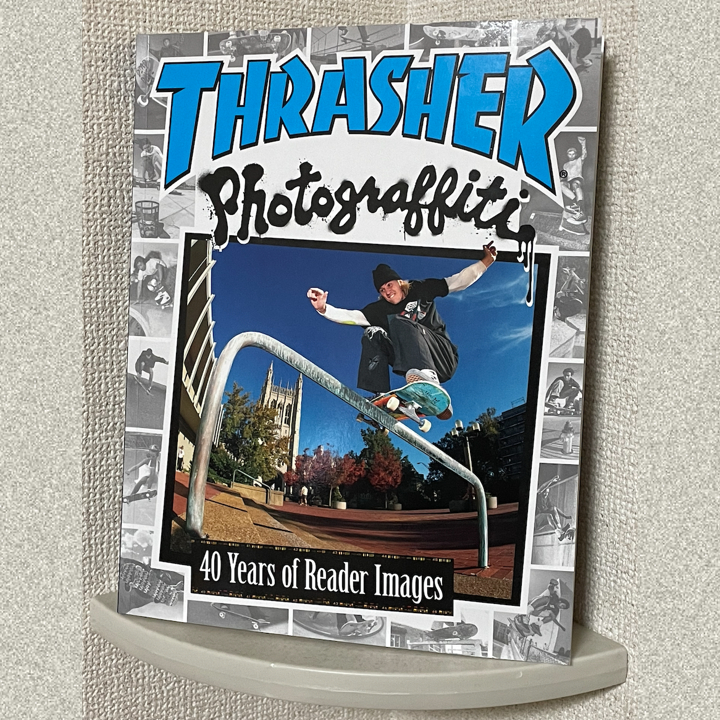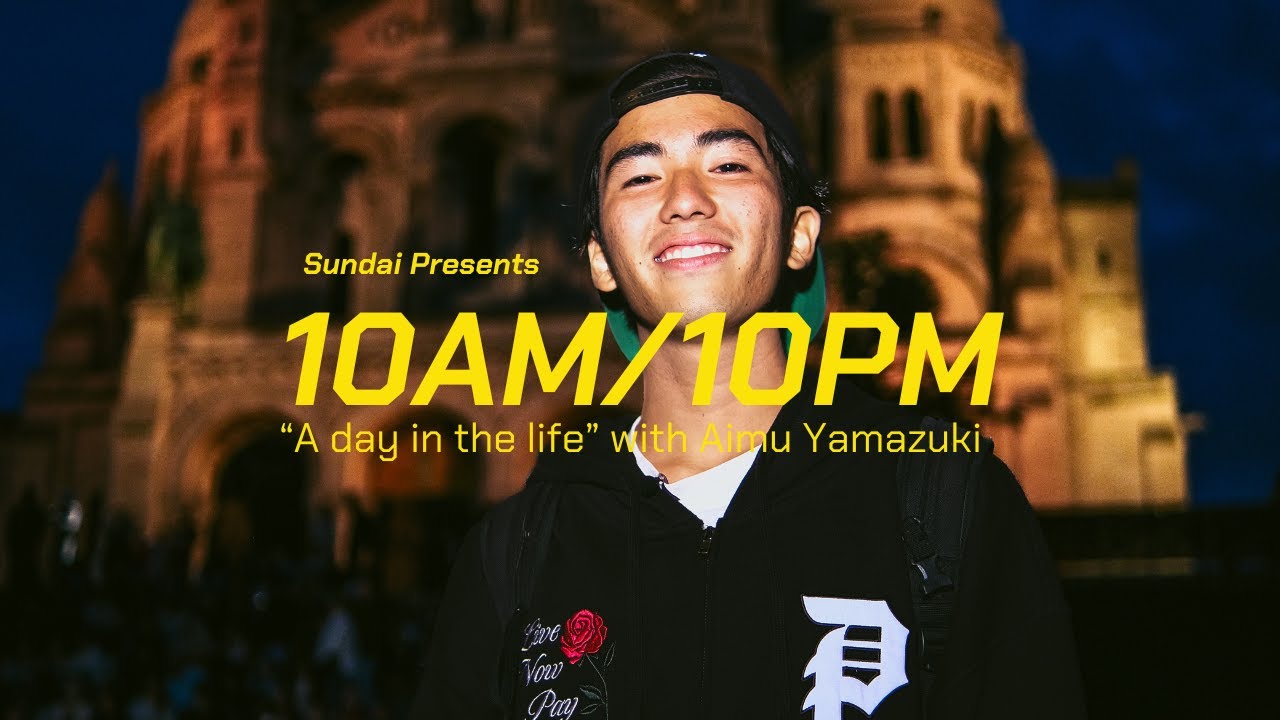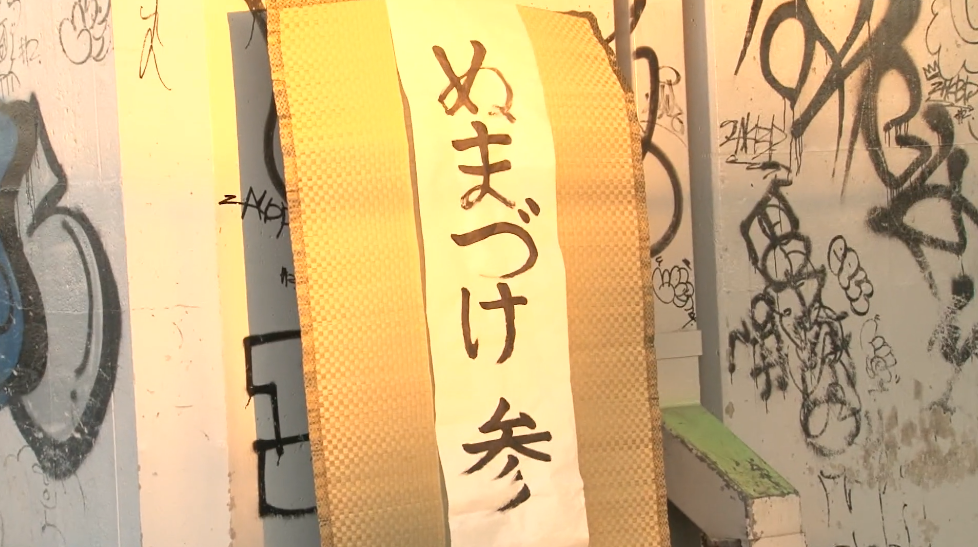HOSOI SKATEBOARDSやG-SHOCKに所属するプロとしてグローバルに活動する芝田モト。テクニックとスタイルを持ち合わせたハイブリッドなバートスケーター。
──MOTO SHIBATA

[ JAPANESE / ENGLISH ]
Photos_Yoshiro Higai
Archive photos courtesy of Moto
Special thanks_Simple City
VHSMAG(以下V): まずスケートを始めたのは? 親父さんの影響が大きいんだよね?
芝田モト(以下M): 父親がもともと'70年代にバートをやってて、僕が生まれたくらいのときに一度スケートをやめたのかな。だから僕がスケートを始める前から大会や『Animal Chin』だったり、父親のスケートビデオが家にあったんです。それで小学校3年生くらいの頃にスケートがやりたいと思うようになって、父親が最後に乗ってたSanta Cruzか何かの8インチのデッキを持って家の裏でチックタックをやってました。それから自分の身体に合ったサイズのデッキを買ってもらって練習してたんですけど、それを見てた父親もまたスケートをやりたいと思うようになって。一緒にクオーターランプを作ったりしてました。それでスケートをやる同級生も増えていって、近所でストリートをするようになって。基礎を覚えた頃にパークに行き出したのかな。それでまた父親もバートを滑るようになって。当時、父親と一緒に滑ってた同年代の人たちもちょうど同じタイミングでスケートを復活したんですよ。僕はその世代の人たちをずっと見てたから、バートを滑るのが普通になってました。しかもその時代の滑り方というか、家に転がっていたビデオで観た滑り方。キックフリップをするんじゃなくて、インバートとかワンフットとか。

V: ちなみにSimple Cityが実家なの?
M: そうですね。このショップはもともとバイク屋だったんです。父親がハーレーに乗ってて、カスタム専門の店。それで2006年くらいにスケートショップに変わったんですよ。それから父親もほとんどバイクを触らないくらいスケートに夢中になって。傍から見たら父親は僕のためにスケートをやってるみたいに思われるかもしれないけど、お互いただスケートしてるだけ。スケートを教えられることもなかったし、ルーティンも自分がやりたいようにやってたし。いろいろ思う人はいるだろうけど、僕らはずっとそんな感じかな。
V: 昔から'80年代のスケートビデオを観て育ったってことだけど、特に影響を受けたスケーターは?
M: 基本的にこの技はこの人がかっこいいというのがそれぞれあって。たとえば、メソッドはクリスチャン・ホソイ、マドンナはトニー・ホークとか。スミスはキャバレロとか。それでトータルで好きだったのはホソイとかバッキー(・ラセック)とか。言い出したらきりがないけど。
V: 昔は南港にAscotっていうパークがあって親父さんもそこで滑ってたと思うけど、アゴローくん(野田敏行)とか宮崎 努くんといった関西のバートスケーターの存在は?
M: もちろん知ってます。一緒に滑ったりもしてたし。僕の父親が先輩で慕ってたりもしてて、僕のことも同じスケーターとして見てくれたり。僕が初めてGスケートパークの13フィートのバートでドロップインしたときも、努くんがたまたまいて。「ランプから突き落としたろか。そしたら速攻行けるわ」って言われましたね(笑)。その後もちょくちょく一緒に滑ったりとか。アゴローくんもそうですね。

V: 日本はバート人口があまり多くない気がするけど、当時は切磋琢磨するライバルとかそういうスケーターはいたの?
M: 僕がバートやり出した頃は周りにプロはいなかったけど、昔Ascotで滑ってたような父親の同世代がいたから。それにGにしかバートがないからみんなそこに集まって、ふたつ年上のバートスケーターもいたり。僕の印象だと当時のほうが賑わってたかな。純粋にバートが好きな人らが自然と集まってた感じ。今はちょっと雰囲気が違いますね。アメリカなら'80年代からやってた人たちが滑り続けてるけど、日本はどんどんやめていって…。賑わって滑ってた当時の人たちがいなくなったから。僕の世代はバートスケーターがほとんどいないですね。今は…あんまり良くない言い方になるかもしれないけど、ランプの横に親御さんがコーチみたいな感じでいて、子供が滑ってっていう…。時代が違うから今は今の形があるとは思うけど、カリフォルニアに行って滑ってたらまだトニー・ホーク、ケヴィン・スターブ、キャバレロがいる。無名な人でも'80年代から滑り続けてる人がいる。そしてその世代の人たちを下の世代がリスペクトしてる。それがずっと続いてるから、ガキんちょでも割り込むことなく絶対にターンを譲ったりするし。自分がバートを滑り出したときの雰囲気を思い出すんです。やっぱこういうのがいいと思いますね。
V: たしかにアメリカは世代が続いてるから成熟してるよね。
M: たとえばバートの歴史とかをみんなちゃんと知ってるんですよ。カリフォルニアでそういう会話をしてると、僕が小さかった頃を思い出させてくれるというか。アンディ・マクドナルドも「真面目か!」っていうくらい詳しいし。向こうで滑るのが面白いのは、知ってる者同士だから話が合うというのと、滑るときのツボが合う。特定のラインを知ってるとか。そういうのが面白いですね。日本も歴史が続いてたらカリフォルニアと同じようになってたかもしれないけど、世代が変わって人が抜けていくから、スポーツのようなスケートボードの在り方になっていくのはしょうがないのかなとは思いますけど。日本は日本のスケート、アメリカはアメリカのスケート。決して同じにはならないかもしれませんね。遅れてるというより、文化を知らない人が多い。
V: そもそも海外に行くようになったきっかけは何だったの?
M: 初めての海外の大会は13歳のときにアジア枠で招待された上海のAsian X Gamesですね。その後は2009年にLAで開催されたX Gamesのアマコンテスト。当時はペドロ・バロスとか、今も一緒にX Gamesに出てるスケーターもいましたね。


V: 初めてのアメリカはどうだったの?
M: 日本人以外の同世代の滑りを見ることがそれまでなかったから、それが衝撃だったかな。同い年で高く飛んだりマックツイスト決めてたり。もちろんその前に上海でアンディ・マック、ニール・ヘンドリックス、レントン・ミラーとかと滑ってたわけだけど、やっぱり同世代の滑りやプロの練習に刺激を受けました。帰国してから自分の滑りが急激に変わったのも実感しました。それまではGのランプで滑ってるだけだったけど、向こうの14フィートのランプを滑ったり。そういう経験を積めたことで意識が変わりましたね。「アメリカに行けば上手くなる」って言う人がいますけど、それとは違うんです。日本でしっかり滑ってたキャリアがあるからこそ、カリフォルニアで得るものがあったわけで。修行するために手ぶらで行っても得るものはあまりないと思いますね。
V: バートランプ自体も日本とアメリカではやっぱり違う? アメリカに行き始めた頃は揉まれた?
M: そうですね。日本でバートって言ったら13フィート。向こうは13.5から14フィートとか。僕がずっと滑ってたGのランプは基本的にインラインスケート用に作られてるから、スケート的にはアールやボトムが短いんです。そういう違いはあるし、海外の大会は1日2時間の練習が3〜4日間設けられるけど僕みたいな下っ端がランプに入れるのは1日15分くらい。プロも同じ練習時間しかないからターンの取り合い。そこに食いついて入っていくのはすごく難しいし、絶対に入れさせてくれない。しかもランプも日本の滑り慣れたものとは全然違う。予選落ちするのはもちろんわかってるけど、いい滑りで終わりたいし。そうやって大会の前日にようやくランプに慣れるっていう…(笑)。向こうの人らはそのサイズのランプで毎日滑ってるから普通だけど、僕はまず慣れるところから始めて、プロに食らいついてランプに入って…。しつこくやってたら逆に「行けよ」って言ってくれたり。気持ちで負けてコーピングにテールすらかけれない日本人もいたし。入れないヤツは消えていく。でも入ってくるヤツはガキでも「先に行け」って言ってくれて、技を決めたらもっと入りやすくなる。そんな環境で揉まれたかな。
V: 2009年に初めてLAのX Gamesに出場して、オースティンで銀メダルに輝いたのが2016年。その間の7年くらいはどうしてたの?
M: 日本でAJSAとかに出てました。アメリカにはまったく行ってなかったですね。調子が良くなくてどん底まで落ちたこともあって。バックサイドエアーすらできなかったりとか(笑)。そのときは必死で調子を戻して…。要はそれまでは感覚でやってて、理屈が抜けてたっていう。そうやって徐々に調子が戻ってきて、2014年に大会とか関係なくアメリカに2週間行ったんですよ。今の自分の滑りが実際どのレベルなのか確かめようと思って。あとは上海とかアフリカとかの大会には出てたけど、ずっとX Gamesからは声がかからなかったんです。僕は出たいけど招待されないと出られないし。X Gamesでドロップインして一発目で終わるヤツとかを観ながら「オレのほうが絶対に上手くやれるのに」って思うことがずっとあって。そういうこともあったから他の大会に出ることが多くなって2016年に自分の滑りが認められたっていうか、無名でタイトルを持ってるわけでもなかったけどX Gamesの招待枠に選ばれたのかな。自分のなかで何のプレッシャーかわからないけど「絶対に決めてやる」って感じでした。
V: その結果が銀メダルだよね。それで翌年にX Gamesミネアポリス戦で見事金メダルを獲得したっていう流れだよね。
M: 前年が2位だったから絶対に優勝しようっていう意気込みでしたね。特にX Gamesのためっていうわけじゃないんですけど、スケートをやってたらひとつくらい自分だけの技をやりたいという思いがあって。それで周りが言うところのカミカゼができたんですよね。僕はフロントのゲイツイストの回転が得意だから、そこに同じく得意なインポッシブルを混ぜたらヤバいんじゃないかなと思って。本当にできるかわからないけど、遠征先の練習中にもちょくちょくトライしてメイクできるようになったんですよ。でもX Gamesが近づいて準備万端ってときに膝の靭帯を伸ばしちゃって…。とりあえずアイシングしまくってニースライドができるくらいまで回復させたものの、まだ膝がグラグラで。でも療養中にかなりイメージしてたから、怪我する前よりもいい感じだったんです。そんな感じでアメリカに行って練習で初めて披露したらめっちゃ盛り上がって。それで本番でも決めれたから優勝できたっていう。あのときはホッとしましたね(笑)。
V: 完璧なランだったもんね。ちなみにカミカゼって名前は誰がつけたの?
M: 練習中にニール・ヘンドリックスとリンカーン・ウエダが来て、「X GamesはTVで放映されるし技の名前を決めたほうがいい」って言われたんですよ。正直、名前なんてどうでもよかったけど…。「なんでもいい」って伝えたらニールが「カミカゼはどう?」って。「それでええんちゃう」って感じでした(笑)。だからニールが提案してくれて広まりました。
V: フロントのゲイツイストを多用する人はあまりいない印象だけど、あれは意図的に選んだトリックセレクションなの?
M: たぶんフェイキーから入る技が自分に合ってたのと、自分が見てたスケーターがそれ系の技が多かったっていう。自分のフロント回りはイケてないと思うこともあったけど、とりあえずやりたかったから。それでゲイツイストのマドンナとかやってて、結果的に自分にしかない技が目立つようになったっていう感じかな。僕は人がやってない技を意地でもやるっていうのはあまりイケてないと思うんですよ。自分がいいと思ってる技が結果的に独特だったっていうのがその人のスタイルになるんだと思います。
V: ゲイツイストのマドンナもあまり見たことがないような気がする。
M: あれはトニー・ホークがやってたんですよ。子供の頃にたまたま観たビデオでやってて、そのイメージがずっと頭に残ってて。いつかやりたいって思ってました。その技について共感できるのは本人のトニー・ホークだから、「脚を抜いてテールを当てるために回転の動きを止めるのは難しいよね」って言われたり。最終的に「あれはモトの技だ」って言ってくれました(笑)。
V: ヤバいね。ちなみにカミカゼはジャパンエアーに続いて日本で生まれたトリックだよね。所属するG-SHOCKは日本のブランドだし、Hosoi Skateboardsもオーナーのクリスチャン・ホソイが日系アメリカ人。海外で活動するときに日本人としてのプライドみたいなものは背負ってるの?
M: 僕は逆にそういうのが嫌いだったかな。スポーツ番組でよく言う「日本人の侍魂」とか「日本人がやっとここまで来た」とか。そういうのがめちゃ苦手で。日の丸のためにスケートしてるんじゃないし、それは他所でやればいいって思う。
V: なるほどね。いまはHosoiからシグネチャーデッキもリリースしてプロとして活動してるんだよね?
M: その前に僕はGreen Issueにずっといたんですよ。バッキー、エイドリアン・ディメイン、スティーブ・サイズとかコアな連中が集まるブランド。X Gamesで優勝した後にGreen Issueからシグネチャーモデルが出て、その翌年の2018年にVans Pool Partyで初めて滑ったときにクリスチャンもいて。一緒に滑ったりしたんですけど、そのときにHosoiに誘ってくれて。もちろん子供の頃から大ファンだしホソイのモデルは昔から何枚も乗ってたけど断って…。


V: 断ったの…!?
M: ちょうどシグネチャーモデルが出たところだったというのもあるけど、Green Issueに対する仲間意識があったから。「いまは抜けるつもりはないけど、でもいつか行きたいから待っててくれ」って伝えましたね。それでその年末にいろいろあって、Green Issueで続けることが難しくなって。いろいろお世話してくれてた人が将来的にはPowellとかBirdhouseとかのほうがいいって言ってくれたけど、自分のなかではクリスチャンが先に声をかけてくれてるからHosoiに行くことにしました。そしたらその人は勝手にBirdhouseの件でトニー・ホークに連絡したらしくてトニーにも誘われて。めちゃめちゃ悩みましたね。トニー・ホークとクリスチャン・ホソイから誘われたら…(笑)。
V: '80年代の頂点ふたりでしょ? しかも子供の頃にずっとビデオで観てたヒーローだよね。
M: そうなんですよ(笑)。結局、ホソイのブランドから自分のデッキを出したいっていう子供の頃からの夢があったから。それをクリスチャンに伝えたら「いますごい飛び跳ねてる!」って喜んでくれて(笑)。それで昨年にVansの大会にもう一度出たときに、クリスチャンから「何時に到着?」とかしつこく連絡が来てて。僕はボウルで身体を慣らしてそのまま帰りたいから飯とかも断ってたんですよ。時差ボケもあったし。それでVansのパークでクリスチャンと合流して4時頃には帰ろうと思ってたら「用事があってちょっと離れるけど5時まで絶対に帰るな」って言われて…。それで滑りながら待ってたらエリック・ドレッセンとかと一緒に何か背負いながら戻ってきたんですよ。それでみんなを集めてケーキを出してきて…。「誰かの誕生日かな?」って思ってたら、「モト、Hosoiへようこそ!」って。「あ、オレか」って感じでした(笑)。そこから長々とスピーチをしてくれたんですよ。それでその後にシグネチャーモデルも渡してくれて。「すげえ!」みたいな(笑)。
V: それは鳥肌ものだね(笑)。
M: 「これを秘密にするの大変だった。モトが日本を出る前から言いたかった」って。「ああ、だからあんなにしつこかったんや」って思いましたね(笑)。クリスチャンはVansのライダーだから大会のときにサプライズをやるのもいいかなって思ってたらしいけど、先に自分のデッキをもらってそれで滑ることができたし、ボウルでどこまでできるかもわからなかったけど…。でも3位に入賞できてクリスチャンも喜んでくれたから、すごく思い入れのある大会でしたね。

V: 子供の頃のヒーローのブランドのプロになるってどういう感覚なの?
M: うれしいし信じられないという感覚はあったけど、一緒に滑ってたらただのスケーター同士だから。逆にいまのバートに関してはクリスチャンが知らないところもあるし。だからいまのバートについて教えてあげたりとか(笑)。
V: そうだね。芝田モトはテクニックとスタイルの両方を持ち合わせたハイブリッドだからね。世代が代々と繋がってるカリフォルニアの成熟したシーンを見てきて、日本のバートシーンに欠けてると思うことは?
M: それを口にしても、僕の言うことを理解してくれる人はいないと思うから…だから言っても仕方ないのかな。でもこないだ東京で滑ってたら小山久史さん(日本で初めてマックツイストをメイクした人)がいてうれしかったり…。そういう人と一緒に滑ってる空間は、アメリカでトニー・ホークとかキャバレロと滑ってるのと同じ感覚でした。日本にもバートの文化はあるところにはある。だからアメリカとか日本とか関係ないというか。

V: たしかに。ところでまったく話は変わるけど、スマホを持たない理由は?
M: ああ…。それは…使う必要がないから(笑)。
V: (笑)。いまは新型コロナで渡航制限とかあるだろうから大変だけど、今後の展望は?
M: 渡米できるようになるまでは、イベントとかをハングリーに待ちながら準備をする感じです。この先、X Gamesとかがどうなっていくかわからないけど、バートの大会でやりたいことのイメージはあるから。でも自分のバートが欲しいというのがありますね。やっぱり新型コロナの影響でパークが閉まったこともあったし、自分のランプがあればトラブルに左右されないし。さらに海外の大会でランプに慣れるところからスタートする必要もなくなるし。だからいつ実現するかわからないけど、いろんな意味で自分のランプを持ちたいという夢は叶えたいところではありますね。

Moto Shibata
@motoshibata
1995年生まれ、大阪府出身。世界を舞台に活動するバートスケーター。2017年にはX Gamesミネアポリス戦で見事ゴールドメダルを獲得。スポンサーはHosoi、G-SHOCK、Monster Energy、Vans、Independent、Bones、PRO-TEC、187、Simple City。